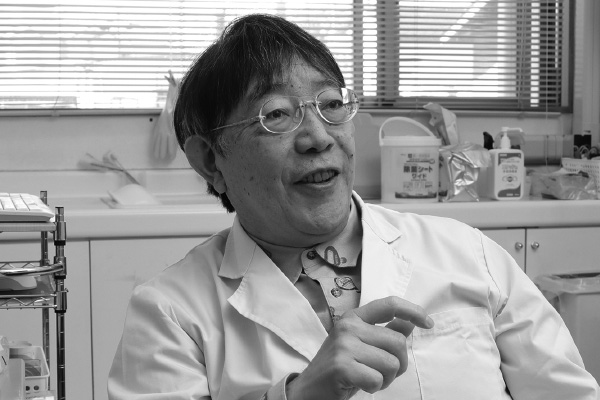
医療法人社団勝医会 副理事長
ふかやクリニック(埼玉県深谷市)院長
古閑 比斗志/㊤
52歳の時、脳幹に梗塞を発症。脳が不可逆的な損傷を受けて、半身が動かせなくなった。一時は職務復帰も諦めたが、“攻めのリハビリテーション”の末、病前とほぼ変わらない力を取り戻した。臨床に加えて、長い在外経験を生かした執筆や講演活動など、多忙な日々を送る。
土曜の昼下がり意識を失い倒れる
予兆は全くないまま、2012年6月9日、運命の日を迎えた。当時の古閑は、厚生労働省職員として関西国際空港検疫所に勤務しており、対岸に関空を臨む官舎に一人住まいだった。土曜は少しゆっくり朝寝をし、昼からは掃除をしながら、NHKの大河ドラマの再放送を見るのが、定番だった。その朝もそのはずだった。しかし、椅子から身を起こした途端、身長174cm、体重73kgの体躯がドサッと床に崩れ落ちた。
そのまま意識を失い、しばらく横たわったままだった。その間は文字通り夢見心地、まばゆい光の中でまどろんでいた。脳が傷害を受けた結果として、エンドルフィンやエンケルファリンという、いわゆる脳内麻薬が大量に放出されていたのだった。この世のものとは思えない心地良い時間は、1時間近くもの間続いていた。後から振り返れば、まさに臨死体験であり、死ぬのは怖くないとさえ思えた時間だった。
やがて次第に意識が戻り、目を開けると、ぐるぐると視界が回り、頭も重かった。立ち上がろうにも、バランスが取れないどころか、手足を満足に動かすことさえできなかった。特に左の手や足には、全く力が入らなかった。古閑はとっさに、「中枢神経がダメージを受けた。脳幹出血に違いない」と確信した。
めまいに堪えかねて目を閉じると、またも夢の世界に引きずり込まれそうになる。そのままの状態を続けていれば、絶命していてもおかしくなかったが、最後は理性が勝った。「まだ死ねない。救急車を呼ばなくては」。
目覚まし時計替わりにしていた携帯電話は寝室のテーブルの上にあった。動かない手足で這って全身を運び、電話を手にするまで一苦労だった。辛うじて動かせる右手でボタンを押した。すぐに消防本部につながったが、ろれつが回らず言葉が出ない。ゆっくりと、脳出血を起こしたらしいことを伝え、官舎に救急車を差し向けてもらうよう頼んだ。「りんくうセンターに運んでほしい」。最も重要なメッセージだった。
りんくう総合医療センター(大阪府泉佐野市)は地域の急性期中核病院で、三次救急に対応した高度救命救急センターを備えていた。死に瀕した今、そこでなければ助からないと古閑は考えた。職務上、例えばエボラ出血などの重篤な患者が見つかった場合はそこに搬入する手はずで、実際に尋ねて隔離室などの装備を確認し、院長とも面識があった。
幸い、電話越しに古閑の危機は伝わった。最後に「玄関の鍵を開けておいてください」と電話が切られた。しかし、これが難題だった。今いる部屋から廊下を通って玄関まで辿り着けるものか。いざとなれば、官舎の管理人が鍵を開けてくれるだろう。またも廊下を這いずり、玄関へと進んだ。這々の体で鍵を開けると、そのまま力尽きて、靴の上に倒れ込んだ。
救急隊が到着した頃、古閑の意識は朦朧としていたが、望み通り、りんくう総合医療センターに搬送された。脳神経外科医とは初見だったが、「脳幹出血のようだから、CTを撮ってもらいたい」と頼み込んだ。「どうやら命は取り留めたようだ」。
途上国で医務官を歴任し検疫所に
古閑のキャリアは、医師として異色だ。1960年に千葉県船橋市に生まれた。子ども時代はSFや石ノ森章太郎などの漫画が好きで、科学者になりたいと思っていた。父は小学校教員をしていたが、祖父は医師で、戦前は満州で開業し父もハルビンで暮らしていた。敗戦を迎えると、大半の日本人は命からがらの目に遭い、祖父も人民裁判にかけられた。しかし、日本人だけでなく、現地の中国人たちの診療も広く引き受けていたため、現地の人たちが嘆願してくれ、祖父一家は解放されて引き揚げ船で帰国した。自分が医師になる夢を砕かれた父は、長男である古閑に、ことあるごとに「医者になれ」と吹き込んだ。
古閑は地元の進学校である千葉県立船橋高校に入学。父は成績にも口うるさく、50番以内の成績を維持することが必要だった。医学を学んだ上で学者になろうと、医学部を受験することにした。共通一次元年と言われた79年、取り寄せた多くの願書の中から、射程圏内の愛媛大学に首尾良く現役で合格した。
入学試験まで足を踏み入れたことがない土地だったが、“坊ちゃん”よろしく青春を謳歌した。古閑の母方の祖父は外交官で、戦前は北京の大使館に勤めていた。大学生の古閑は、外務省の医務官という仕事を知り、両親双方の祖父の道を受け継げる、その職に就こうと思った。
89年に医学部を卒業すると、船橋市内の自宅近くに開院したばかりの千葉徳洲会病院で修業を積んだ。現在のように各診療科を回る初期臨床研修ができる同病院を選び、まず脳神経外科からローテーションを開始した。最速で臨床の実力を付けようと選んだ病院で、2日に1度の当直をした。かつてサイボーグ研究にあこがれた経緯から、脳神経外科医を目指した。神経学的所見の取り方や、CTやMRIなどの画像診断についてもみっちりと学んだ。
結局、手術の技量には限界があると早々に悟り、外科の道は断念したが、当時蓄えた脳の知識が、四半世紀を経て、倒れた際の咄嗟の判断に生きた。「三つ子の魂、今もあの訓練が我が身を救う判断につながった」。
その後、内科に転じて消化器内科で修行を積んだ後、95年外務省に入省、モンゴルに医務官として赴任。ホンジュラスやアフガニスタンでも勤務した。海外の医療事情を考えれば、倒れたのが日本だったことも幸運だったと思える。
さて、りんくう総合医療センターに運ばれた古閑は、幸いCT では脳に出血が認められなかった。しかし、MRIの結果から、脳を栄養している4本の動脈(左右の内径動脈と椎骨動脈)のうち、右の椎骨動脈が解離を起こしていると判明した。ここから血栓が飛んで、脳幹が梗塞を起こしたものだという。左半身が麻痺しているのも納得できる。古閑が医師だということが分かったので、主治医の説明も専門的だった。
脳幹出血という自身の診立てはやや外れたが、重症であることに変わりはない。たばこは随分前にやめていたが、動脈硬化は間違いなく原因になっているはずだ。「このまま手足が動かないままで、どんな人生が待ち受けているのだろうか」。(敬称略)
【聞き手・構成】ジャーナリスト:塚﨑 朝子




古閑Drと同じ愛媛大学の卒業生(1981年卒)です。言葉がおかしいですが、面白くよみました。自分自身は整形外科医ですが、松山リハビリテーション病院という回復期リハビリテーション病棟が主の病院に勤務していますので、若年発症の脳幹梗塞の患者さんが多くいます。続編を楽しみにしています。