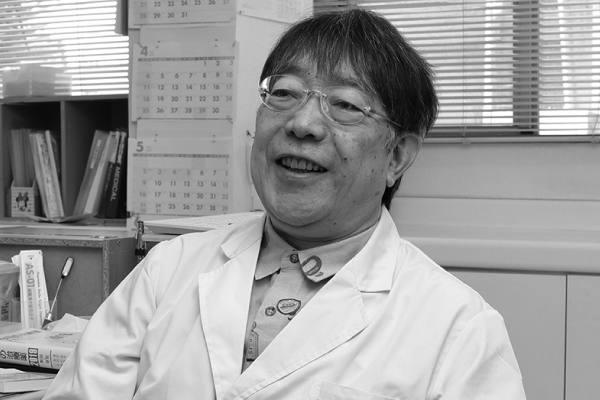
医療法人社団勝医会 副理事長
ふかやクリニック(埼玉県深谷市)院長
古閑 比斗志/㊦
 大病をした患者は大勢見てきた。80代の父も2010年に脳梗塞で倒れた。しかし、その翌々年、52歳という働き盛りの自分が脳幹梗塞に倒れるとは、衝撃だった。臨死状態から意識が戻り、最善の救急病院に搬送されていたことも幸いし、復活の日々を送っている。
大病をした患者は大勢見てきた。80代の父も2010年に脳梗塞で倒れた。しかし、その翌々年、52歳という働き盛りの自分が脳幹梗塞に倒れるとは、衝撃だった。臨死状態から意識が戻り、最善の救急病院に搬送されていたことも幸いし、復活の日々を送っている。
救急車で運ばれた先は、りんくう総合医療センター(大阪府泉佐野市)。右の椎骨動脈が解離して血栓が飛び、脳幹梗塞を発症したため、血栓溶解療法は行えず、脳保護剤のエダラボン、再発防止を目的とした抗血小板療法のための薬が投与された。
3日間ICUで過ごし、急性期の症状が落ち着いてきたことから、一般病棟の個室に移った。入院は、小学校4年生の時に虫垂炎になって以来だった。その時は大部屋で同室の大人たちにトランプに誘ってもらったりしながら、退院の日を指折り数えて心待ちにしていた。
左半身に麻痺が残り言葉も十分に発せず
今回は、危うく命拾いはしたものの、動かぬ左半身に加えて、嚥下障害、言語障害、複視を抱え、医師としての職場復帰はおろか、普通の社会生活さえ望み薄に思えた。とにかく早期からのリハビリが必要とのことで、まず手足を動かす訓練から始めた。
嚥下障害については、主治医に「口から食べられないままなら、胃瘻にしましょう」と言われ切なかった。しかし、東京から駆け付けた家族を前に笑顔が戻ってきた。「水羊羹を買ってきて」「アイスクリームが食べたい」と、ここぞとばかりに甘えた。そして、家族のためにもリハビリに力を入れようと自らを鼓舞した。3人の子どもたちは大学生、高校生、末っ子はまだ小学生だった。
急性期の治療が一段落すると、継続的なリハビリのための転院が必要だった。そこに救いの神が現れた。愛媛大学医学部入学時に1級下だった酒向正春は、その4月に開院したリハビリ専門病院、世田谷記念病院(東京都世田谷区)に、副院長として着任していた。酒向は、元は脳神経外科医で脳卒中を専門に据えていたが、リハビリの可能性に開眼し、脳リハビリ医に転向していた。「俺のために作った病院じゃないか」と思えるほどで、まさに“渡りに船”だった。
6月25日に転院した。立ち上がることさえできず、車椅子での移動で、医師が同伴しなくては飛行機に搭乗できない。古閑の2歳年下の弟は脳神経外科医で、東京の病院に勤めていたが、快く迎えにきてくれた。
世田谷記念病院で、365日間、早朝から夜間まで、“攻めのリハビリ”が始まった。機能訓練はもちろんのこと、日常生活動作能力を向上させ、早期の在宅復帰を目指すのだ。思い通りにならない体は鉛のように重く、できれば横たわっていたかった。しかし、午前中から否応なく車椅子に乗せられ、リハビリ室に連れて行かれた。午前、午後、さらに夜も、多様なリハビリメニューをこなした。2週間経つ頃には、両足で立てるまでになり、クラッチ(杖)による歩行訓練に進むことができた。 「土日も休まないから、効果が持続されるのだな」。
古閑は生来右利きだったが、子どもの時から、左手でも字を書き、細かい作業をこなせるような訓練をしていた。その結果、脳の両側が鍛えられ、右側の言語中枢も発達したようだ。それが機能回復を早めたと感じている。
やがて杖に頼らずとも移動できるようになり、退院の日を迎えた。退院後の住まいは、目黒区内の国家公務員宿舎。そこから通院リハビリを始めた。病院までは、二子玉川駅からバスで向かう。帰りに駅に行くためのバス停は多摩川の土手の上にあり、よたよたと道路を横切ろうとして、何度も車に轢かれそうになった。そして2カ月の自宅療養の後、12年9月に職場に復帰した。倒れた時の古閑は単身赴任で関西空港検疫所に勤務していたが、元通りの生活には戻れず、東京検疫所に異動させてもらった。
毎日の通勤に付き添ってくれた上司
関西時代に上司だった山内久は、少し先に東京検疫所に赴任していた。古閑の通勤経路では、2度の乗り換えが必要だった。同じ路線で4つ先の駅に住んでいた山内は、毎朝古閑の乗る電車に先乗りして、乗り換えを手助けしてくれた。通勤ラッシュの時間帯、足取りの覚束ない古閑が、何とか通勤できたのは、山内のお蔭だった。
言語障害が残り、頭も十分回転しているとは言い難かった。職場では、降格して課長となったが、実務は部下に任せることができた。しばらくは“お飾り”の上役にすぎなかったが、何とか決裁のために押印だけはした。
社会生活に戻ってみると、世の中はバリアだらけだった。例えば、道路は真っ平ではなかった。降雨時に排水できるよう、中央が盛り上がり、端は緩やかに傾斜している。足を取られて転びそうになった。透水性舗装の平らな道路にすれば、自分も高齢者ももっと安全に歩けるだろうに。「今まで普通と思っていたことが、実は正しくなかった。バリアフリーといっても言葉だけだ」。
古閑は復帰から半年後の13年2月末、外務省、厚生労働省と渡り歩いた宮仕えにピリオドを打った。そこからクリニックに内科医として勤務し、渡航者の健康診断などを行った後、大手プラントメーカーの産業医に転じた。途上国も含めて海外に赴任する社員が多く、渡航先で支障がないよう、現地の医療事情を調べ、万が一の時には高度な医療が受けられるよう手配した。在外公館に勤務した経験が活きた。その後、民間病院を経て、20年3月から、現在のクリニックに院長として勤務する。高齢の患者が多く、介護保険によるリハビリやデイサービスなども併設している。
10年間仕事を続けていくうち、大病したとは思えないほどの機能回復を果たした。言語は滑らかで、片足立ちも難なくできる。唯一残った後遺症は左半身と右顔面の温痛覚障害だ。入浴時に左足が熱い湯に触れてもよく分からないことには違和感があるが、その程度で済んだ。
患者たちにかつての自分の闘病経験を話すと、一様に驚き、「私もリハビリを頑張らにゃ」と言ってくれる。未曾有のコロナ禍と向き合う中で、豊富な知識と実務経験に基づき、『ウイルスと外交 メディカル・インテリジェンスの舞台裏』という著作を出した。関連して、講演会などに呼ばれることもある。海外在留邦人の心と身体の健康をサポートするための特定非営利活動法人JAMSNET東京では監事を務めており、渡航医学について助言をすることもある。
「今日があるのは、酒向先生の攻めのリハビリと、山内さんや家族を始めとして、支え続けてくれた人がいるから」
“人間性の回復”というリハビリの理念が、心に深く染み入っている。(敬称略)
(聞き手・構成)ジャーナリスト:塚﨑朝子


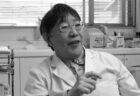

LEAVE A REPLY