
がん治療はその後のQOL(生活の質)も不可欠な要素となるが、その中で重要ではありながら正面から取り組まれる機会の少なかった課題に妊娠がある。若年者のがんが増えたり、小児がんの治療成績が上がったりで治療後の妊娠の可能性を求める患者も多い。がん治療と「妊よう性温存」の研究をする鈴木直理事長に聞いた。
◆ 学会設立の経緯を教えてください。
鈴木 研究会として立ち上げたのは2012年です。がん治療と妊よう性の温存について正しい知識と情報を医療関係者と患者に届けたいということが目標で、根底にあるのは「がん治療を優先する中で、将来の妊娠の可能性も追求する」という考え方です。当初は生殖医療にがん治療医が土足で入った感じで驚かれましたね。また、あるがん学会でセミナーを開催しようと協賛企業を探したのですが、十数社に断られました。その中で1社だけが「がんが治ってからの妊娠出産は少子化対策にもなる」と応援してくれました。結果的にそのセミナー会場は満員でした。みなさん、関心は高いのですが、情報が少ないのです。そのような中、仲間と分担して全国の講演やシンポジウムで、この問題を医療関係者にも患者さんにも訴えて来ました。認識は広がり、17年4月には妊よう性温存に関するガイドラインが発行されるまでになりました。
◆ この領域に目を向けたのは?
鈴木 自分は婦人科腫瘍医なので、元来妊よう性温存を諦めなければならない婦人科がん患者と現場で向き合ってきました。新婚旅行から帰ってきたばかりの20代後半の女性が進行がんと分かり、妊娠出産どころではなく命のために子宮を取る選択をしたり、15歳の女の子に子宮頸部横紋筋肉腫が見つかって子宮を摘出したりというようなシビアな状況を経験してきました。一方で、生殖医療の分野では技術が進み、がん治療の知識があいまいなまま妊よう性温存が図られることもありました。生殖医療の現場からすると温存する技術があるのだから妊娠の準備もしておきましょうということなのでしょうが、あくまでもがん治療が優先です。そのようにあいまいな部分のあったがんと生殖の医師をつなぐ役目として研究会を立ち上げようと思いました。
卵子や卵巣の凍結で妊よう性温存
◆ どのように妊よう性を温存しますか。
鈴木 進行がんなどですぐに治療が必要なケースは対象になりません。がん治療開始前の妊よう性温存療法には、卵子や受精卵の凍結保存、卵巣組織の凍結保存などがあります。男性には精子の凍結保存があります。がん治療の副作用を説明する中に「将来妊よう性がなくなる可能性があります」という説明があるべきですが、がん治療を目の前にした患者さんに伝えるのはなかなか難しく、それがこれまでは抜けていました。がん治療を優先とする中で、妊よう性温存をするかしないかはあくまで患者さんが決定することで、自己決定を促すサポートが重要です。
◆ 妊よう性温存が注目されたきっかけは何ですか。
鈴木 04年にベルギーで画期的な報告がありました。25歳のホジキン病患者さんが閉経を招く抗がん剤治療の前に卵巣を摘出して凍結保存し、治療が終わった5年後に卵巣を身体に移植して妊娠、出産に至ったというものでした。これがこの世界のブレークスルーになり、欧州を中心に取り入れられて妊よう性温存の新たな方向性となりました。日本では、06年からサルを用いた前臨床試験を行っており、卵巣組織凍結はどこまでできるかという成果を4年で出しました。10年からは臨床試験で100人以上の卵巣を凍結保存しています。
◆ 妊娠、出産についての考え方を聞かせてください。
鈴木 産婦人科は子供の福祉を考える集団なので、妊娠したら終わりではありません。子供を産んで、子供たちが成長して幼稚園、小学校、中学校に行きます。そして高等教育を受けて家を出て結婚するまで子供を見守るのが出産なのです。そこまではお母さんは元気でいなければいけません。がん患者さんの中には「がんで死んでも赤ちゃんがほしい。夫が育てる」という人もいますが、本末転倒です。治療開始までの時間的余裕があって卵巣、卵、精子を凍結しておけば将来にチャンスがあるという、正しい情報を正しいタイミングで伝えることが患者さんの利益になります。
がんと闘う意欲と希望へつなげる
◆ 妊よう性を温存する意味は大きいですね。
鈴木 がんの状態次第で治療後に妊娠する可能性を残すことは、患者さんが治療に希望を持って臨む意欲に大きく作用します。18歳の女性が卵子1個を保存し、その写真を壁に貼って抗がん剤のつらい治療に耐えたことがありました。大切なのは、妊よう性について医師から説明を受け、自己決定すること。治療後に妊よう性温存の方法があったと知っても遅い。医師に余裕がなければ、看護師に「将来の妊娠に不安はあるか」「聞きたいことはあるか」と問診票でチェックしてもらい、患者の意思を確認する方法も有効です。
◆ ガイドライン作成以外の成果を教えてください。
鈴木 国のがん対策推進計画が昨年改訂されましたが、がん対策推進協議会は「生殖機能温存」の6文字を盛り込みました。厚労省も実態調査に動き出し、研究班が三つできましたが、そのうち私は心理士との連携を担当しています。日本生殖心理学会と我々の学会が協働して、今年から「がん・生殖医療専門心理士」の養成講座も始めました。生殖医療の心理の専門家にがんを分かってもらいます。妊よう性を残せる人、残せない病状の人それぞれへのケアに加え、夫婦関係の改善も期待されます。「がん離婚」といいますが、卵子を保存して40歳でホルモン治療が終わっていざ卵子を戻そうとしたら離婚している人が少なくありません。10代で抗がん剤治療を受けて生理が戻っている人で21歳にもかかわらず実は卵巣機能は35歳相当ということもあります。知らずに30歳前後で結婚したらすでに閉経していることもあり得ます。このような小児がんサバイバーに「卵巣機能が落ちている可能性があるから結婚するなら早めがいい」と伝えることもできます。
今後の学会の在り方は?
鈴木 妊よう性を残せる可能性があるのか、可能性があるなら産婦人科を紹介するというのは当たり前のルールになるべきです。時にはがん治療を優先するため妊よう性温存を諦めるしかないと伝えなければなりません。ヘルスケアプロバイダーといいますが、医師、看護師、心理士、薬剤師、ソーシャルワーカーらが一体となって患者を守ることが大切です。また、単一診療科ではなく乳腺科、泌尿器科、小児科、血液内科などが協力していかなければなりません。全てのがん治療医が本領域を理解して、それぞれが妊よう性温存について考えてくれる時代が来れば、この学会の役割は果たせたと思います。



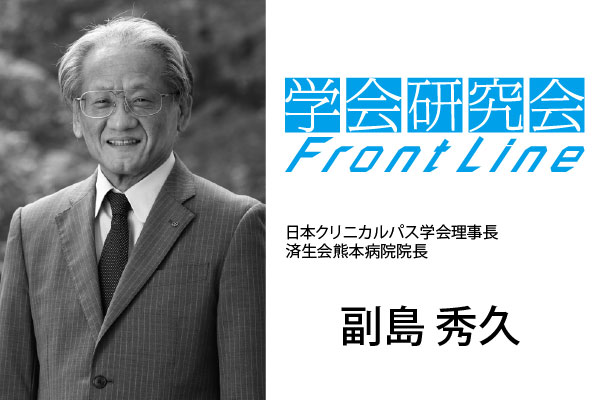
LEAVE A REPLY