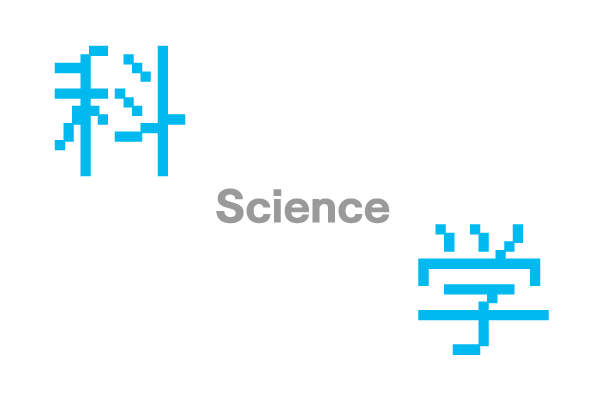
再生医療が残してきた実績と今後の進展を考える
2006年、京都大学の山中伸弥氏が、人工多能性幹細胞(iPS細胞)をマウスで作製し、翌07年にはヒトでも樹立する事に成功した。山中氏は、10年に設立された京大iPS細胞研究所(CiRA)の所長に就任、12年には早くもノーベル生理学・医学賞受賞の栄冠を射止めた。まだ医療への応用が緒に就いたばかりの段階での受賞だった事から、当初からポテンシャルの高さが注目されていた。
翌13年から、政府は、10年で実用化する事を目指し、iPS細胞を始めとする再生医療研究に対し、10年間で1100億円規模の長期的な支援を約束した。iPS細胞の医療応用の歩みは着実に進み、成果が出始めている。
iPS細胞技術が残した確実な成果
22年4月、大阪大学の眼科学教授である西田幸二氏らは、iPS細胞から誘導した角膜上皮を、世界で初めて4人の患者に移植した臨床研究の結果を報告した。対象疾患は「角膜上皮幹細胞疲弊症」で、3層構造の角膜で最も外側にある角膜上皮の幹細胞が感染症や薬の副作用等で消失、角膜が混濁する等して、視力障害から失明に至る事も有る。治療には角膜移植しか無く、従来はドナーから提供される角膜が頼みの綱だった。しかし、ドナーは世界的に不足していて供給数は少なく、拒絶反応も高確率で生じ、移植しても生着しないケースが多かった。
西田氏らは、京都大学でストックしているヒトiPS細胞から角膜上皮前駆細胞を誘導して単離し、ここからヒトiPS細胞由来の角膜上皮組織を作製する技術を確立している。動物モデルへの移植実験で安全性と有効性を評価し、作製した細胞に造腫瘍性が無い事も確認している。臨床研究の移植後の経過観察期間は1年で、終了後も更に1年間追跡調査を行う。
主要評価項目は安全性だが、副次評価項目として、疾患の改善度合いや視力の回復等の有効性も評価する。移植用の角膜上皮前駆細胞は厚さ0.03〜0.05mmで、これを直径3.5cmの円形のシート状にして移植する。細胞数にして数百万個程、これが角膜を作り続ける為に、角膜の透明性を保持すると期待されている。
19年7月から、重症の4例(30〜70代)に対して移植が実施された。iPS細胞由来の細胞は拒絶反応が起き難いが、他家移植になる為、4例のうちHLA型が一致しない最初の2例は免疫抑制薬を使用した。残る2例では、拒絶反応や腫瘍形成等、重篤な有害事象が無かった事から、HLA不適合でも免疫抑制薬を投与せず実施されたが、安全性に問題となるような有害事象は認められなかった。
又、有効性では、4例とも角膜の濁りが消え、白内障の併発により評価が難しかった1例を除き、日常生活に支障が無い程度迄視力が改善した。最も著効を示した例では、矯正視力が0.15から0.7に迄改善したという。
これらは文字通り大きな光明となる成果で、今後は標準治療迄高める事が期待されている。大阪大学発の医療ベンチャーである「レイメイ」(大阪市)は、臨床試験(治験)を23年度にスタートさせ、最短で25年度中の承認による実用化を目指すという。
iPS細胞研究中核拠点の動き
iPS細胞のいち早い実用化の為、日本医療研究開発機構(AMED)の支援で再生医療実現拠点ネットワークプログラムが開始され、「iPS細胞研究中核拠点」として、4つの主要なプロジェクトがスタートしている。すなわち、脊髄損傷(慶應義塾大学・岡野栄之氏ら)、網膜(理研からビジョンケアに移った高橋政代氏ら)、パーキンソン病(京都大学・高橋淳氏ら)、心筋細胞(阪大・澤芳樹氏ら)である。
世界で初めてiPS細胞由来細胞の移植を行ったのは、高橋政代氏である。14年、患者本人のiPS細胞から網膜細胞を作製し、加齢黄斑変性の患者に移植する手術を実施した。その後、患者以外の他人のiPS細胞から作った網膜細胞の臨床研究も主導している。住友ファーマが、加齢黄斑変性を対象として治験に向けた準備を進めている。
パーキンソン病では、高橋淳氏らが、iPS細胞ストックからドーパミン神経前駆細胞へと分化させ、患者の脳に注射で注入し移植する治療の臨床研究を実施した。住友ファーマと共同開発中で、24年度の実用化を目指して、国内で第1相、第2相の医師主導治験が進められ、米国でも22年度からの治験を計画しているという。
又、心筋では澤氏らが、iPS細胞から作製した心筋細胞をシート状にして、外科手術によって重度心不全の患者の心臓に貼り付ける医師主導治験を、19年から実施している。
脊髄損傷では21年12月、慶大病院でiPS細胞から作った神経細胞を脊髄損傷の患者に移植する世界初の手術が実施された。岡野氏(生理学教授)と中村雅也氏(整形外科学教授)が主導し、19年に臨床計画が承認されていたが、新型コロナウイルス感染症の対応等で開始が遅れていた。脊髄損傷から2〜4週間経過し、完全麻痺が有る亜急性期患者、計4例に対して実施の予定で、1年かけて安全性や有効性を検証するという。患者は、通常の地はビリテーション治療等も併用しながら、副次項目として運動機能の改善等を評価される。
これ以外にも、京都大学ではiPS細胞から血小板を作製して、血小板輸血不応症を合併した再生不良性貧血の患者に移植する臨床研究も実施されている。又、血小板減少症の患者に対し、あらかじめ健常者由来のiPS細胞から血小板の元となる細胞を作製しておき、血小板製剤として輸血する治験の準備も進められている。
重症心不全患者に対して、慶應義塾大学ではiPS細胞から作った心筋細胞を球状に加工して患者の心臓に注入する臨床研究の準備を進めている。更には、難治な癌の治療等を目指した基礎研究も続々と進められており、芽吹きを待っている。
再生医療のこれから
iPS細胞の臨床応用への歩みは堅調だが、今後は、いよいよ真価が問われる段階に突入する。最大の課題は、政府からの重点支援が22年度で終了し、その先の支援が見通せない事だ。研究機関や大学でシーズを育てた後、その成果を実用化し普及させようとすれば、ベンチャー企業等との連携や、民間資金をいかに活用していくかも鍵になってくる。
再生医療は、薬に比べて適応となる患者数が少ない為、細胞調製等に多額の費用が掛かれば高額な治療になりかねない。コストを抑える為には、iPS細胞大量自動培養装置等、治療を支える為の周辺技術の開発も進めて行かなくてはならない。経済産業省によれば、iPS細胞を含む再生医療の市場規模は、50年に世界で38兆円に達すると試算されている。
世界はコロナウイルスとの闘いに、未だ苦慮している。一方で、癌に代表されるように、人類がまだ克服出来ない難治疾患は幾つもある。治療の切り札として大きく期待される再生医療で、日本発のiPS細胞を用いた治療を開花させる事は、日本のみならず、世界に貢献出来るものだ。
iPS細胞の樹立から15年の節目を迎え、山中氏は22年3月末でCiRA所長の座を退き、後継を高橋淳氏に託した。退任に際して、山中氏は現状をマラソンに例え、「中間点の折り返しを過ぎた所」と評している。
前半戦は、治療に使える質の高いiPS細胞を安定的に作製する事に力を入れた。後半戦、そしてラストスパートには、より多額の研究資金が必要だ。退任後も、「iPS細胞研究財団」理事長として、企業との連携や資金確保の支援を続けて行くと言う。日本発の研究成果の正念場を見守りたい。







LEAVE A REPLY