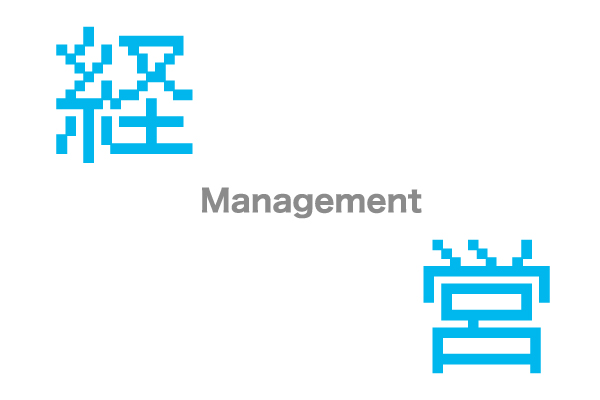
適応範囲の見極めと有効性・安全性のエビデンスの蓄積を
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックは、病院経営に大きな影を落としている。6月に発表された日本病院会や全日本病院協会等のまとめによれば、4月時点で全国の3分の2の病院が赤字に転落。外来では、感染リスクを恐れて受診患者が減少した。入院については、院内感染を防ぐために病棟を減らさざるを得ないため、制限せざるを得なかった。そんな中で、入院、外来、在宅と並び、“第4の診療形態”としての「オンライン診療」が、改めて注目されている。それどころか感染の第2波、第3波に備えて、諸外国と比べて遅れの目立ったオンライン診療を含めた遠隔医療を更に充実させ、定着させなくてはならない時期に来ているようだ。
日本では、オンライン診療の議論は、コロナ禍が始まる前から中央社会保険医療協議会(中医協)等で進められていた。遠隔医療そのものは、実は半世紀近い歴史がある。2005年には、日本遠隔医療学会が設立されている。学会によれば、日本では1970年代から遠隔医療への取り組みが始まったが、本格化したのは90年代。96年に厚生省(当時)で、遠隔医療研究班(班長=開原成允・東京大学教授)が立ち上がった。当初は、画像伝送を中心とした取り組みが多く、研究班は遠隔医療を「映像を含む患者情報の伝送に基づいて遠隔地から診断、指示などの医療行為及び医療に関連した行為を行うこと」とした。その後、学会発足と共に定義が進化していった。
厚生労働省は、2019年に改定した『オンライン診療の適切な実施に関する指針』の中で、遠隔医療を「情報通信機器を活用した健康増進、医療に関する行為」と定義している。また、同指針においてオンライン診療は、「遠隔医療のうち、医師-患者間において、情報通信機器を通して、患者の診察及び診断を行い診断結果の伝達や処方等の診療行為を、リアルタイムにより行う行為」とされた。
東日本大震災を機に実質的に解禁
近年遠隔医療が注目を集めたのは、11年3月の東日本大震災である。東北地方の沿岸部は壊滅的な打撃を受け、医療従事者の死亡、医療施設の損壊、診療記録の破損、流出等の甚大な被害が契機となって、政府の方針は、遠隔医療、電子カルテ・ネットワークの推進へと大きく転換していった。15年の厚労省通達では、遠隔診療は「離島や僻地に限るものではない」とされ、これが実質的なオンライン診療の解禁と解釈されている。
そして、20年年明けから始まったCOVID-19の拡大。対応策の一環として、従来は再診に限っていたオンライン診療を、特例的・時限的に初診から行う事が解禁された。電話等による初診は「受診歴なし」でも可能となり、初診料214点は対面診療より低く設定された。
病状が安定している患者であれば、長期処方で経過を診ていくのも1つの手だ。しかし、不安定な病状を抱えていたり処方薬剤を調整したりする必要がある場合は、定期的なオンライン診療でフォローアップしていく事は有用であろう。
また、発熱や倦怠感などでCOVID-19罹患を心配する患者等にも、オンライン診療で不安の解消に繋げられ、場合によっては対面診療を行う判断が必要になる。保健所への問い合わせの混雑を解消して、より的確なトリアージに繋げられた事例等もあるという。
日本プライマリ・ケア連合学会では、20年に『プライマリ・ケアにおけるオンライン診療ガイド』を発行している。中では、オンライン診療がふさわしいか否かについて、以下の5つの条件を確認する事を掲げている。すなわち、(A)医師患者関係(相互の信頼)(B)患者が情報通信機器に慣れていない場合、接続方法やコミュニケーションを助けるオンライン診療支援者がいる(C)診療に必要な患者登録手続きが済み IDが発行されている(D)診療報酬上の初診か再診か(E)対面診療への切り替えに関わる重篤な急性症状や慢性疾患の増悪はないか。また同ガイドでは、適切例と不適切例についても具体的なケースを挙げて紹介している。
院内情報共有や感染リスク低減等も実現
遠隔医療はプライマリ・ケアに限ったものではない。医師同士を繋ぐ仕組みもある。例えば、集中治療専門医チームのT-ICU(兵庫県芦屋市)が提供するシステムは、チームの専門医が、現場の非専門医と電子カルテの情報等を共有する事で、24時間365日、アドバイスを与える仕組み等が実用化されている。救急医療の専門医が開発した仕組みで、2次救急医療機関である、さくら総合病院(愛知県大口町)で導入されている。
院内で活用する情報共有のための仕組みもある。COVID-19患者を受け入れた病院では、患者が入るエリアには陰圧スペースを設ける等、病棟内をゾーン分けして通常の診療と切り離さなくてはならなくなった。
例えば、聖マリアンナ医科大学病院(神奈川県川崎市)では、COVID-19患者に治療に当たる医療スタッフが、オンタイムで情報を共有するためのツールを導入した。アルム社の「Join」というソフトウエアを用いれば、スマートフォン上で検査画像を確認出来、関係者全員が即座に共有してチャットする事も出来る。患者のデータはもちろん、会議録なども共有出来る。
また、感染リスク低減のため、別室から遠隔操作で向きやズーム等を容易に操作出来るウェブカメラも利用した。患者だけでなく、人工呼吸器画面と体外式膜型人工肺(ECMO)やバイタルサインのモニターといった画面データも確認出来る。
神戸市立医療センター中央市民病院でも、患者と職員の接触機会を減らすための遠隔通信システムが導入された。病室にウェブカメラとタブレット端末を設置して遠隔で病状を見守り、呼び掛けも出来る。控え室にいる家族との面会にも使われた。
現在、遠隔モニタリングを行うために様々なデバイスが開発されている。こうしたデータが蓄積すれば、むしろ病状の推移を評価しやすくなるといった利点が生まれる可能性もある。そして収集されたデータは、今後は人工知能(AI)と組み合わせる事で、医療変革に繋がると見込まれている。専門医療の集約化によって、専門医がなくなった地域の医療にも貢献出来る。
今後、遠隔医療・オンライン診療を更に普及させ、定着させるには、いくつかの条件がある。オンライン診療では、まずその適応を医師がきっちり見極める事である。対面の診療と比べて優劣を競うものではなく、医師の判断に基づいて適当であると判断した場合に選択される診療形態である。そして医療である事から、重視しなくてはならないのは有効性や安全性についてエビデンスを蓄積していく事である。それが医師にとって、形態を選択する際の判断材料にもなる。
日本社会は、医療も含めて旧態依然とした仕組みをなかなか変えられない。コロナ禍で、せめてプラスになった事として、遠隔医療やオンライン診療を育てていかなくてはならないだろう。




LEAVE A REPLY