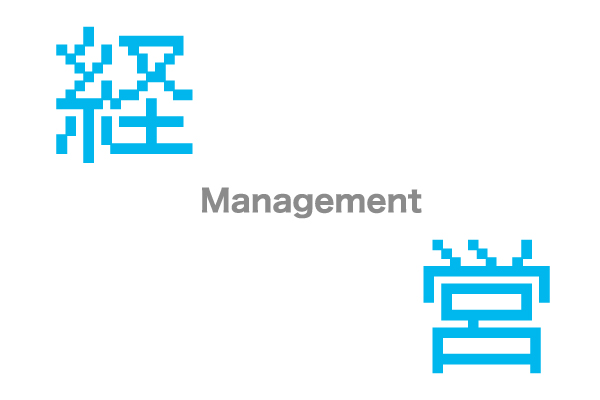
「価格交渉力に長けた薬剤師」の 育成で経営改善
2018年のノーベル医学生理学賞は、京都大学特別教授の本庶佑氏らに贈られることが決まった。本庶氏は、免疫の“司令塔”であるT細胞表面に免疫活動にブレーキを掛ける免疫チェックポイント分子「PD-1」を発見し、小野薬品工業と共に抗PD-1抗体である「ニボルマブ(オプジーボ®)」を開発した。免疫療法は、手術、放射線、薬物に次ぐがん治療の第四の柱と期待されながら、長らく目ぼしい成果を出せないでいたが、本庶氏らの発見により新たな扉が開かれた。
2014年7月に世界で初めて日本で発売されたオプジーボは、当初、年間約3500万円とされる高額の薬価ばかりが注目された。しかし、世界中で年間約900万人の命を奪うがんに対して、新たな治療法が切り開かれたという点では、人類にとってプライスレスな薬である。
医療現場において、薬価はこれまで以上に重要な課題である。少し、日本の薬価制度について振り返っておきたい。オプジーボの薬価は、2017年度から一気に“半額”に引き下げられることでも話題を呼んだ。
日本では、治験を経て厚生労働省の製造販売承認が得られた後、中央社会保険医療協議会(中医協)で公定価格が決まる。欧米諸国では製薬企業と保険者など支払い側の交渉や市場価格に基づいて決まるのに対し、日本には明確なルールに沿っている。この薬価算定方式は「類似薬効比較方式」と「原価計算方式」に大別されるが、各薬について算定理由は公開されている。
前者は既に類似した薬効の薬がある場合に、それと比較しキャップをはめる形で決められる。比類ない薬であったオプジーボの薬価は原価計算方式で決まった。抗体医薬の原価は高い上、世界初の承認なども加味されて、営業利益率は平均(16.9%)の6割増しの27.0%に加算された。
さらに、まず手術不能な悪性黒色腫(メラノーマ)への適応拡大が承認されたことが、薬価を引き上げた。当初、発売後5年間の市場規模は、ピーク時の2年目で患者470人、販売額31億円という数字が根拠となった。
病院支出に大きく占める薬剤費
さて、免疫療法はそのメカニズムからして、がん種に依らず効き目が期待され、オプジーボは、希少な難治がんから、非小細胞肺がんや胃がんなど、患者数の多いがんへと次々に適応が追加承認されており、なお適応拡大を目指して多くの治験が実施されている。
こうした状況に配慮して、薬価のルールが急遽変更された。薬価の見直しは2年に一度の診療報酬改定で見直される。加えて、2016年度からは、年間販売額が極めて大きい品目は、「特例市場拡大再算定」の対象となった。オプジーボの販売額が1500億円超と算出されたため、特例で最大の50%引き下げが、2年を待たずして実施された。
院内に話を移そう。病院における薬剤費は、支出全体に占める規模が大きい。また、診療における影響という点から、薬剤は最も重要な購買品目と言える。前述の通り、日本では公定価格が定められており、病院が自由に価格を設定する余地はほぼないため、薬価が意味を持つのは、コスト抑制という観点からである。
さて、従来から、ある薬剤を採用するにあたっては、製薬企業の医薬情報担当者(MR) が、処方元となる医師を相手に自社製品をPR し、採用に至るというのが古典的な図式である。そこでは、病院経営の視点や経済的合理性は、ほとんど顧みられていない。
オプジーボの例を見ても明らかなように、医学の進歩に従って、これから登場する薬剤はますます高額なものになるはずだ。そこで、新薬の採用に際しては、有効性や安全性はもちろんだが、経済性も加味して、多方面から評価するという姿勢がますます重要になってくる。
薬価の交渉においては、事務部門が窓口となることが多いようだが、そこには、医師、薬剤師も当事者として加わり、組織として対応していくことが求められる。広く院内で情報を共有し、患者にとっての有用性だけでなく、病院の経営への貢献という観点も加味する必要があるだろう。
全医薬品の値引き率は、薬価改定のあった年には、急激に悪化する傾向が見受けられる。薬価差益がなお、病院の経営に対して持つ意味合いは小さくないことを、再認識しておくべきである。
次に、病院、医薬品卸業者、製薬企業の関係も踏まえておきたい。ある薬が採用されそうになると、薬剤部は製薬企業に対して医薬品卸業者の帳合を打診し、指定された卸業者から薬剤を購入することになる。卸業者は顧客を獲得する際に、製薬企業を利するような方向に動くことがあり、病院を含めた三者の協議や単品の価格交渉などは難しくなる。
病院・製薬企業・卸業者の歪な関係
医薬品の購買モデルは、一般の消費財と異なっている。例えば、卸業者が、買い手に1000円で売り、メーカーから900円で仕入れていれば、100円の利益を得るというのが、一般の商品である。
これに対して、薬剤の場合、まず製薬企業は卸業者に対して、販売価格の建値を例えば90%で仕切るようにする。すると、病院は卸業者から10%以上値引きした金額で購入する。卸業者に生じる赤字部分は、製薬企業から「売上割戻し」や「報奨金」という形で利益補償されている。卸業者には製薬企業に対する価格交渉力が機能していない。卸業者の最終利益率が1%前後なのに対して、製薬企業は30%近くを確保している。
病院は本来、価格決定権を持つ製薬企業と価格の交渉をすべきで、そうした取り組みをする病院も少しずつ増えているようだ。交渉に際しては、病院が分析したデータに基づく交渉であることを明確にするため、まず薬剤部が使用実績のデータから購入金額上位品目を抽出していくことが必要だ。また、病院に対する販売価格の加重平均値(税抜きの市場実勢価格)も確認して、十分なデータを整理した上で交渉に臨んでいくことが重要になってくるだろう。
かつては、「総価取引」で包括的に値引きを定めて取引率を決める方式により、価格交渉する病院が多かったが、オプジーボのような高額薬剤が多数登場している現状では、病院側の利点は少ないと考えられている。今後、こうした交渉実務に長けた薬剤師を養成することは、大きく病院経営に寄与することが期待される。




LEAVE A REPLY