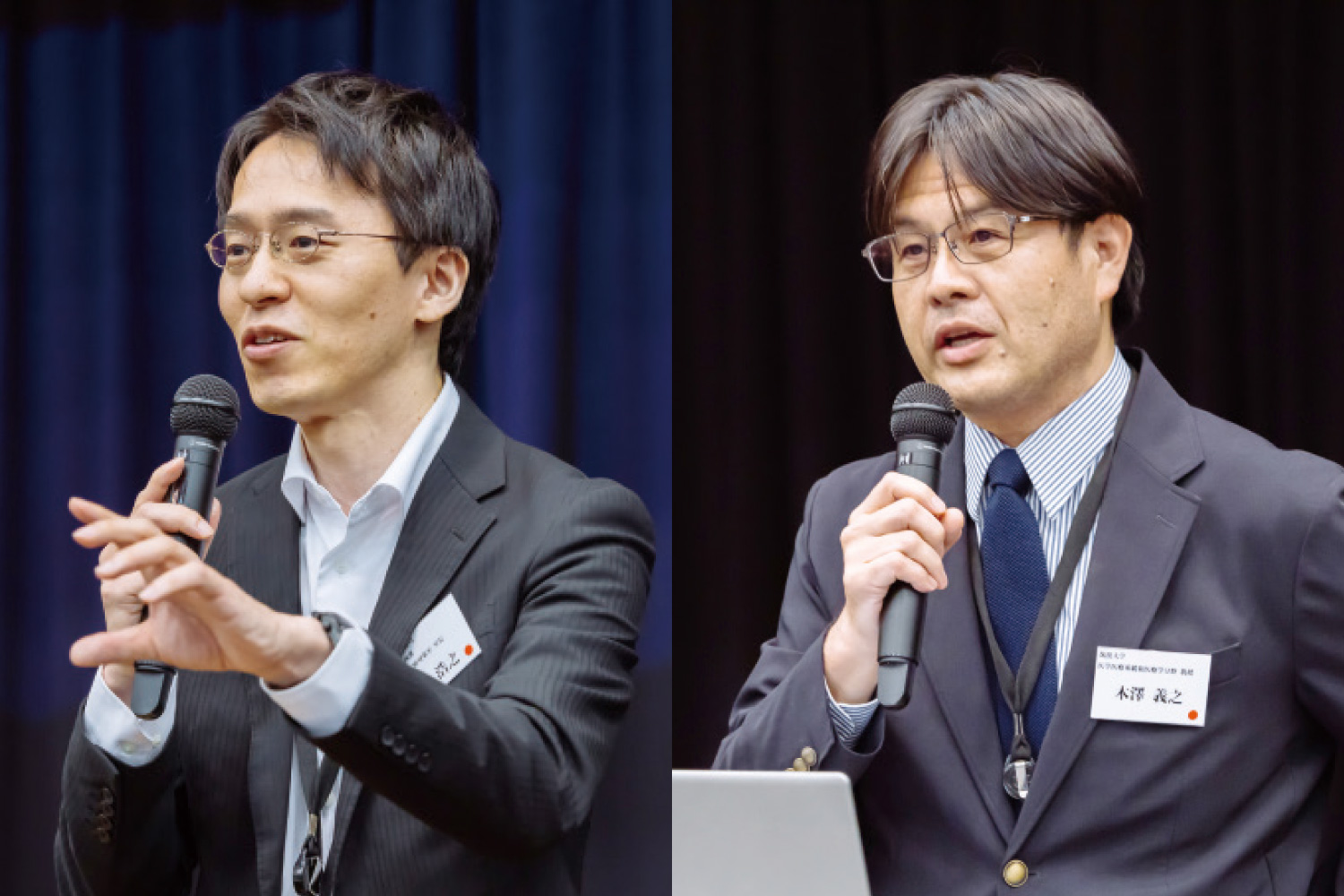
挨 拶
原田 義昭氏 「日本の医療の未来を考える会」最高顧問(元環境大臣、弁護士):政治の世界では、米トランプ大統領の言動に注目が集まっていますが、少しやり過ぎではないかと感じる事が有ります。一方で、あれ位の破壊力が無ければ、世の中は動かないとも感じます。ウクライナでの紛争も、トランプ大統領の破壊力が事態を終結へと動かすのかも知れません。日本の政治家も、時には強力な破壊力が必要ではないでしょうか。
三ッ林 裕巳氏 「日本の医療の未来を考える会」最高顧問(元内閣府副大臣、医師):一般の人達の間でACPの普及はまだまだ進んでいないのが現状ですが、認知症の患者や意識の無い人の意思をどの様に確認し、医療やケアに反映させるのか、医療現場では大きな課題となっています。特に一人暮らし、家族の居ない人への対応には苦慮します。学会でも議論されていますが、国がしっかり指針を定め、それに沿って進めて行くべきです。
古川 元久氏「日本の医療の未来を考える会」国会議員団メンバー(衆議院議員、国民民主党代表代行兼国会対策委員長):長く尊厳死の法制化を超党派で議論していますが、未だ法案の作成には至っていません。又、最近は大学病院等で老年科を廃止する所が増えていると聞きました。高齢化が進む中、病院の老年科は非常に重要で、超党派の国会議員で老年科の在り方を考える議連を作ろうという動きも有ります。ACPもこれらの課題と関連が有り、勉強したいと思います。
和田 政宗氏「日本の医療の未来を考える会」国会議員団メンバー(参議院議員、内閣委員長):自民党で、骨太の方針に関する会議が始まりました。私も「医療や介護、福祉の公定価格を引き上げていかないと現場が崩壊してしまう」と発言してきました。物価や賃金のスライドも含め、しっかり原資を獲得しなければならないと思っています。東国幹財務政務官等ともしっかり肩を組み、現場の人達が現在の苦境から脱する事が出来る様努力していきます。
尾尻 佳津典 「日本の医療の未来を考える会」代表(『集中』発行人):今回は、人生の最終段階での医療・ケアを如何に決定するかという重いテーマを選びました。普段こうした事を考える機会は余り無いのですが、色々勉強をしてみると、やはり日本は欧米に比べて随分遅れている様に感じました。適切で必要な医療を受ける為に、自分で選択をしなければならない時代に、どの様な事が必要なのかを勉強したいと思います。
講演採録
■ACPの現状と国の取り組みについて
講師:厚生労働省医政局地域医療計画課外来・在宅医療対策室 室長 中西浩之
国は2007年、終末期に於いて、本人の意思に沿った医療・ケアが行われる様にする為、「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」を策定しました。これは富山県の射水市民病院での人工呼吸器取り外し事件が契機となりました。その後、15年に「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」に名称を変更し、18年には、病院だけに限らず、在宅医療や介護の現場でも活用出来る様に見直しを行いました。
「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」と「ケア」の文字が入り、医療・ケアチームの対象に介護従事者が含まれる事を明確にしました。又、医療・ケアの方針やどの様な生き方を望むか等を、家族等の信頼出来る者も含めて日頃から繰り返し話し合うプロセスであるACP(アドバンス・ケア・プランニング)の取り組みが重要とし、本人が自らの意思を伝えられない状態になる前に、本人の意思を推定出来る人を前以て決めておく事の重要性も明記しました。「家族等の信頼出来る者」の範囲は、法的な意味での家族だけでなく、親しい友人等を含むより広い範囲の人を意味します。こうして繰り返し話し合った内容は、その都度文書として纏め、必要に応じて家族等と医療ケアチームで共有する事が重要です。
ガイドラインを作成した際の報告書では、普及啓発の必要性が指摘されました。ACPの概念について、多くの国民に知って頂き、適切な取り組みに繋げていく事が重要です。本人がどの様な医療ケアを最終段階に於いて受けたいのか、意思決定する為に支援していく為のものであり、決して医療費の削減の為に行うものではありません。国ではACPの愛称を「人生会議」とし、毎年11月30日を「人生会議の日」と定めました。
又、「人生の最終段階における医療・ケア体制整備等事業」として医療・ケア関係者向けの研修や国民向けの普及啓発活動を実施しています。
■ACPをどの様に考え、実践するか
講師:筑波大学医学医療系緩和医療学分野 教授 木澤義之
医療の質に於いて重要な要素の1つに「十分な説明を受けて納得の上で治療を受けられる」事が挙げられます。ACPは、「意思決定能力が十分ではない人に医療・ケアを行う時に、どうしたら本人の意向に沿った医療を提供出来るのか?」という問いに答える為に生まれたものです。前述の射水市民病院の事件では、意思決定能力の無い終末期がん患者の人工呼吸器を停止した行為の是非が問われました。意思決定能力の無い患者に対し、人生の最終段階に於ける医療・ケアの方針をどの様に決めたら良いかのプロセスが、国のガイドラインには示されています。
ガイドラインでは、意思決定のプロセスは、本人の意思が確認出来るかどうかにより大きく2つに分かれています。意思確認が出来る場合は本人と医療ケアチームが十分に話し合い、所謂インフォームドコンセントのプロセスを踏んで、本人が納得した上で方針を決めていきます。問題は本人の意思が確認出来ない時で、ここでも2つの道筋に分かれます。
先ず、家族等がいて、本人の意思を推定出来る場合は、家族等は本人の推定意思を尊重し、本人にとって最善の方針を考えるというのが重要なポイントです。日本の現在の法律では、家族は医療に関する代理決定をする権利は無いというのが私の理解です。あくまで本人の推定意思に沿って決定するという事であり、本人が信頼している人であれば、知人や友人でも構わないとされています。もう1つの道筋は、家族がいない、又は家族等がいても本人の意思を推定出来ない場合です。この場合は、最善の方針を医療・ケアチームで慎重に判断する事になっています。
日本ではACPを、「必要に応じて信頼関係のある医療ケアチームの支援を受けながら、本人が現在の健康状態や今後の生き方、さらには今後受けたい医療・ケアについて考え、家族等と話し合うこと」と定義しています。そして、医療者の役割は「将来の心づもりについて言葉にすることが困難になりつつある人、言葉にすることを躊躇する人、話し合う家族等がいない人に対して、適した支援を行い、本人の価値観を最大限くみ取るための対話を重ねていく」事、としています。
歴史を振り返ると、「本人が意思を表明出来なくなった時にどうすれば本人の意向を尊重した意思決定が出来るか」という取り組みは、米国で始まりました。端緒となったのは、本人が意思決定出来ない場合に備え、前以て「事前指示書」を作成しておけば、それが本人の意思の代わりになるという制度の導入です。しかしながら、これは必ずしも有効ではない事がその後明らかになりました。
米国の医師会が主導した大規模な比較試験では、事前指示書を書いていた人と書いていなかった人の間で終末期医療の質(患者の痛み、事前指示書の遵守、医療費、患者・家族満足度等)に差は出ませんでした。この様な結果になった原因として、患者の意向が変わる事、家族が患者の意思とその背景に在る価値観等の情報を知らなかった事、事前指示書が直ぐに参照出来る状態ではなかった事等が挙げられています。その後も複数の研究が行われていますが、事前指示書さえ作っておけば解決出来るという事にはならないというのがこれ迄に分かっている事です。
それに代わり大切なのは、本人と家族との話し合いだとされています。人生の最終段階でどの様な医療やケアを受けるかを、前以て具体的に想像したり決めたりする事は困難ですが、その様な場合に何が大切かについては話し合う事が可能です。ACPを適切に行うと、本人と家族の間のコミュニケーションが促進され、本人が望むケアと実際に受けるケアが一致し、家族の不安や抑鬱も減少すると言われています。但し、ACPは自分の人生の最終段階を話し合う事になる為、心の準備が出来ていない方は希望を失ってしまうという問題が有ります。自分が亡くなる時の事を想像しなければならないのは、人によっては辛い事です。もし事務的に「意思決定能力が無くなった時、どの様な医療を受けたいですか」と聞かれたら、患者は途方に暮れるでしょう。この話し合いを円滑に進める為には、医療者のコミュニケーションスキルもとても重要な要素になります。




LEAVE A REPLY