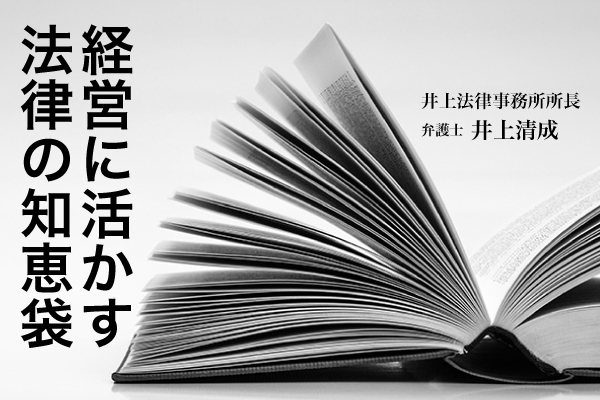
支払基金の権限の強化
2025年6月22日に会期が終了した第217回国会(通常国会)では、内閣提出の「医療法等の一部を改正する法律案」は成立することがなく、秋の臨時国会に先送りとなった。その医療法等の改正法案には、「地域医療構想の見直し」「医師の偏在是正に向けた総合的な対策」などといった重要な項目が含まれている。「医療DXの推進」もその重要な柱の1つであり、社会保険診療報酬支払基金(以下、支払基金)が医療DXの運営に係る母体になるらしい。名称を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」と改め、従来からの審査支払に加えて、医療DX推進計画を担当することとなろう。
しかしながら、権限の強化をするとしたら、その前提として、従来からの「審査事務」に関する信頼回復がなされなければならない。「審査事務に関する信頼回復」を始めとする「審査の充実」がなされなければ、支払基金に重要な「医療DXの推進」を担当させられないであろう。
コンプライアンスの徹底と組織風土の改革
支払基金では、22年6月頃から支払基金支部の約290名が、画面上の「確認済」ボタン等を押下しないままでも一定時間経過後に次のレセプト画面に遷移する「レセプト画面の自動遷移ツール」を使用する不適切行為が行われていたことが発覚し、「公的保険を使った医療費の請求書を不適切な手段で審査していた」などの理由で、職員22人を懲戒処分、ほかの職員267人が文書注意処分を受けることとなった。「自動遷移ツール事案」と称されるが、支払基金による「適正なレセプト審査に対する信頼に関わる問題」として大きな注目を集めた(25年1月31日付け福岡資麿厚生労働大臣の記者会見より)。
そこで、「令和 7 事業年度 社会保険診療報酬支払基金事業計画」において、「コンプライアンス意識の向上に向けては、今回の事案や過去に問題のあった事例等を具体的に反映したケーススタディを活用して、保険者等の関係者から信頼を得ることの重要性や、『悪い情報ほど速やかに報告する』という意識が浸透するよう、全ての職員に対し研修を階層別に実施する」こととし、かつ、「自動遷移ツール事案の反省と、その上に立ってこれまでの取組を改善するため、中核審査事務センター等において、今回の事案がなぜ把握できなかったのか、組織風土改革委員会において検討し、その結果を踏まえ、真に職員の抱える課題や悩みを汲み取ることができるよう、改善を検討する」こととした。
だが、まだ当時のコンプライアンスの不十分さが未解決・未改善のままに残っている事例もあるらしい。他の残された事例も、直ちに解決し改善しなければならないところであろう。
告示に反する検査料・初再診料の取扱い
診療報酬の告示「D282‐3コンタクトレンズ検査料」には
| 1 コンタクトレンズ検査料1 | 200点 |
| 2 コンタクトレンズ検査料2 | 180点 |
| 3 コンタクトレンズ検査料3 | 56点 |
| 4 コンタクトレンズ検査料4 | 50点 |
と定められ、その告示の「注1」には、
と定められている。
ところが、専ら「コンタクトレンズ装用」に着目した診療の場合には、その告示の「注3」に、
と明記され、「初診料」は算定できなくなっていた。なお、「告示」には、法律と同等に権利を付与し義務を課することのできる「法規」としての強い効力がある。
そして、「注3」については、その告示の留意事項として、厚生労働省保険局医療課長発出の通知が出されていて、その第2章第1節第2款D282‐3(4)には
というように、告示の法解釈が明記されていた。
つまり、「過去にコンタクトレンズ検査料を算定した患者に対して」再び「コンタクトレンズ検査料」を算定する場合は、「初診料」は算定できず、「再診料」等しか算定できない、ということなのである。
専ら「コンタクトレンズ装用」に着目した診療に対して、余り診療報酬は算定したくはなく、「初診料」でなく、せいぜい「再診料」程度で済ませたいというのは、まさしくその通りであると思う。
しかしながら、「コンタクトレンズ検査料」を過去に算定した患者に対して再び算定する場合は、専ら「再診料」とし、再び算定しない場合には、たとえ「過去にコンタクトレンズ検査料を算定した患者」であっても、専ら「再診料」しか算定できないとはしなかった。「初診料」もあれば、「再診料」もあるとしたのである。これこそが法の定めであり、その法の落とし所が妥当であったかどうかはともかく、政策的な妥協の産物としての法の落とし所ではあった。
ところが、支払基金は一部で、独自の見解によって、「告示」に対して厚労省保険局医療課長「通知」とは異なる解釈を施し、勝手に運用していたのである。
審査支払のコンプライアンス強化の必要性
実は、支払基金のうち、東京・大阪といった大都市部においてだけは、「過去にコンタクトレンズ検査料」を算定した患者であれば、今回は「コンタクトレンズ検査料」を算定しなくても絶対に「再診料」しか算定できない(つまり、「初診料」は算定できない)としたのであった。
推測ではあるが、大都市部においては、実質的に専ら「コンタクトレンズ装用」の診療をしている医療機関に対して、初診料の請求を特にさせたくなかったのかも知れない。
ただ、支払基金がいくらそう思っても(または、正しいことだとは思っても)、国民健康保険団体連合会や大都市部以外の支払基金の担当者は、「告示」や「解釈通知」に明示的に反する独自解釈や運用まではしなかった。コンプライアンス意識が強かったから、ぐっと堪えて、我慢したのであろう。
したがって、支払基金のうち、大都市部の担当者だけが、コンプライアンスに反する解釈・運用をしたのであったから、支払基金としては、その対応は誤りだったと直ちに認めて、改めるべきである。くれぐれも、話をそらして、「初再診料は、ケースバイケースで算定するだけなのだ」などと弁解して後講釈でごまかそうとするべきではあるまい。
自動遷移ツール事案という不祥事のために、「医療DXの推進」の母体としての適格性に疑義が呈された現時点においては、支払基金は、大都市部における解釈・運用のコンプライアンス違反を直ちに認めて適切に改善し、秋の改正医療法の成立、そして、「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」への移行のための環境作りに励むべきである。
支払基金は、今はまずは、残された未解決・未改善事案の解決・改善をし、審査支払のコンプライアンスの強化に全力を挙げるべきであろう。


LEAVE A REPLY