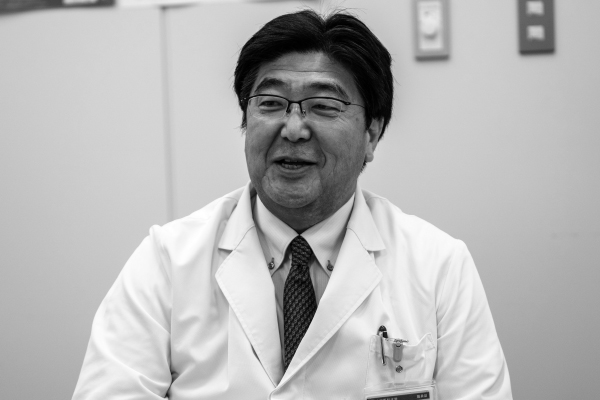
金沢医科大学(石川県河北郡内灘町)
整形外科特任教授
兼氏 歩/㊤
整形外科医になり、股関節を専門として人工関節への置換術を中心に、年間200件の手術をこなしてきた。恰幅は良く、野球で鍛えた体力には自信があった。2017年春、それが過信だったことを思い知らされる出来事が起きた。
学会出張中に腹痛で緊急受診
その年の日本整形外科学会学術総会は、東北大学が主催して仙台で開催された。兼氏は、自身の発表もあり、教育研修講演の座長など、いくつもの役割を背負っていた。健啖家で、仲間たちと土地のグルメを味わうことも楽しみだった。
開催前日、5月17日水曜日から現地に入り、その晩は医局のスタッフと共に懇親会に参加したが、余り食欲がわかず、好きな酒も進まなかった。主任教授の川原範夫は兼氏を気遣って、医療機関の受診を勧めた。
実は、腹痛は1〜2週間前から続いていた。キリキリと痛み、刺身でアニサキスに当たったかなぐらいしか、思い当たる節がなかった。虫垂炎かもしれないと思った。
18日に学会が始まると、シンポジウムの演者として、何とか用意した講演を済ませた。壇上から降りると、会場にいた東北大の医師に、「盲腸かもしれないので、開業医さんを紹介してもらえませんか」と話しかけた。
兼氏の異変を悟ると、医師はすぐ兼氏をタクシーに同乗させて、東北大学病院に向かった。救急外来に車が着くと、スタッフが待ち受けており、すぐに兼氏を検査室まで誘導してくれ、CT検査を受けた。消化器内科の医師の診立てによると、腸が詰まってイレウス(腸閉塞)を起こしかけているとの診断で、入院を勧められた。消化器は専門外だが、急を要する状態であることは、兼氏にも理解できた。ただし、翌日は朝から教育研修プログラムの座長を担当する予定で、外すわけにはいかない。しかし、強い口調で「東北大に入院しますか、金沢で入院しますか」と畳みかけるように尋ねられて、観念した。
座長を代わってもらえるよう仲間に頼み込み、仙台を離れることを決めた。病名は告げられていなかったが、仮に虫垂炎だとしても、そう長く診療に穴を開けることはできなかった。
検査画像と紹介状を携えて新幹線に乗り、金沢医大病院消化器内科の医師に連絡を取った。金沢に戻ると、自宅に立ち寄る間もなくそのまま入院し、大腸内視鏡検査を受けることになった。食べ物も飲み物も取らず絶飲食した結果、何とか便通があった。麻酔で鎮静された状態で検査を終えると、担当した教授は、あっさり「進行がんですね」と、結果を告げた。紹介状にも、がん疑いの記載はあったかもしれなかったが、青天の霹靂とはこのことだ。
野球少年が運動に関わる整形外科医に
兼氏は1965年、濃尾平野の西、愛知県葉栗郡(現・一宮市)に生まれた。尾州と呼ばれるその地の繊維産業は約1300年の歴史を持ち、高度経済成長期には花形産業の1つだった。兼氏の家も、代々繊維工場を営んでいた。ただし、繊維業の勢いは衰えつつあり、両親は、兼氏も3歳下の弟も、好きな仕事に就けば良いと考えていた。
小学校に上がった兼氏は、野球に打ち込んだ。理系科目を中心に学業成績は良く、高校は地元の進学校、県立一宮西高校に進学し、野球にも熱中していた。将来の職業に対して明確な目標はなく、スポーツに親しみ、漠然とスポーツドクターも良いなと考えるようになった。国立大学の医学部を目指すならばと、両親は応援してくれた。担任の教師には現役合格は難しいと言われ、1年浪人して猛勉強の末、金沢大学の医学部に受かった。城下町の落ち着いた雰囲気が気に入り、自宅からの程良い距離も良かった。
大学でも医学部の準硬式野球部に入り、キャプテンを2年務めた。卒業後の進路は決めかねていたが、整形外科には体育会系っぽい雰囲気があり、チームプレーが生かせそうだと、先輩から勧められた。スポーツ外科にも携われそうだった。91年に卒業後、母校の整形外科に入局した。満遍なくひと通り学んだ後は、教授の意向に沿って股関節を専門に据えることとなり、手術の腕を磨いた。99年からは金沢医科大学に勤務しており、2001年には米国トーマス・ジェファーソン大学に留学する機会も得た。看護師の妻との間には、長男・長女に恵まれていた。妻は突然の脊髄の病気で車椅子生活を余儀なくされることになったものの、その後次男を出産し、訪問看護ステーションを経営するまでに立ち直った。バイタリティー溢れる女性で尊敬している。
生活を反省し自院で腹腔鏡手術
家族思いの兼氏だったが、がんを発症した頃は、子育てや家事は妻に頼り切りで、多忙な日々を送っていた。大学では日々の診療に加えて、教育や研究にも携わる。さらに、月に1〜2回は学会や講演が入る。海外の学会に参加することもあった。好きなゴルフは、日曜日にプレーできればよく、慢性的に運動不足で睡眠不足もあり、絶えずストレスを抱えていた。「身勝手に生きてきたかもな」という反省点はある。
がんは想定外だったものの、生活習慣のリスクファクターはほぼ揃っていた。喫煙こそしなかったが、肉が好きで野菜は少なめ、酒は普段はビール1本程度だが、宴席では痛飲することもある。医者の不養生の成り行きだと、自分でも納得する部分もあった。さらに言えば、家系的にもリスクがあった。早期発見で事なきを得ていたが、父は大腸がんと胃がんを患っていた。祖母も胃がんだった。
消化器外科には、金沢大学で1級下だった後輩がいて、大腸を専門としている。親身に相談に乗ってくれた。進行がんであることから、術後は外来で化学療法を受けなくてはならなくなるという。兼氏が執刀する予定の手術は、ギッシリとスケジュールが組まれていた。影響を考慮すると他の医療機関で手術を受ける選択肢はなかった。後輩は、兼氏の手術を快く引き受けてくれた。
手術前には、いくつもの検査があった。造影CTではリンパ節に4カ所の転移が見つかり、「ステージⅢa」と診断された。患部は、虫垂にも近い上行結腸だ。職場の定期健康診断はきちんと受けていたが、大腸がんのスクリーニングとされる便潜血反応で陽性になったことはない。血液中の腫瘍マーカーを調べると陰性だった。仮に人間ドックを受けていたとしても、内視鏡はS状結腸までしかやらないことが多く、がんが早期に発見されていた可能性は低いと考えられた。
深刻な病状とは言え、切羽詰まった感じはしなかった。泰然と受け止めていた。診察に同席してくれた妻も、かつてどん底を経験したはずだが、夫婦揃って、ポジティブシンキングだった。
幸いにも、確定診断から3日後、急患扱いで手術の日程を組んでもらうことができた。病室に横たわって眺める風景は、いつもと違って新鮮だった。病室や手術室では、患者が兼氏であることは伏せられていた。麻酔に身を委ねたと思ったら、次に目覚めたのはICUだった。腹腔鏡下手術で、リンパ節転移を含めて、がんは切除できていた。(敬称略)




LEAVE A REPLY