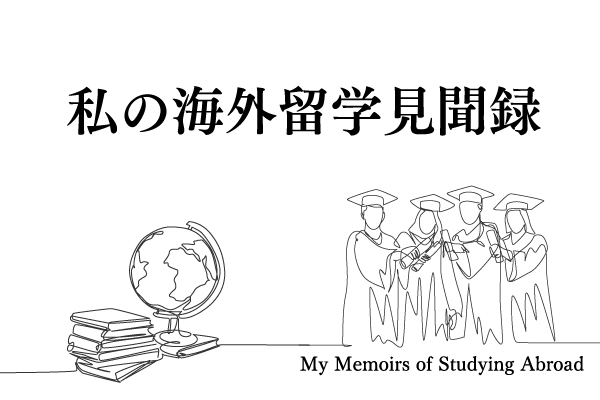
瀧田 盛仁 (たきた・もりひと)
医療法人社団鉄医会 ナビタスクリニック立川 院長
留学先: Baylor Research Institute(現 Baylor Scott and White Research Institute)(2008年10月〜15年5月)
2008年から15年まで、米国テキサス州ダラスのベイラー研究所に留学し、膵島移植の臨床研究に従事しました。東京大学医科学研究所附属病院の血液腫瘍内科で後期研修中から細胞・組織移植に関心を持ち、当時の北村俊雄教授、上昌広教授、そしてベイラー研究所の膵島移植部長であった松本慎一先生とのご縁により、留学の機会を得ました。膵ランゲルハンス島を糖尿病患者の肝内門脈に注入する膵島移植は、1型糖尿病患者に対する同種移植のほかに、慢性膵炎患者に対する全膵臓摘出後の自家移植として注目されています。現在、私は東京都立川市の駅ナカで、国籍を問わず多様な患者様の一般内科診療に携わっておりますが、留学経験は日々の診療の大きな糧となっています。
留学のきっかけと膵島移植との出会い
留学前の私は病棟での診療に追われ、学術活動と言っても症例報告を書く程度で、Phase I・IIの前向き試験を担う力量は全くありませんでした。言語の壁もありました。そんな私を、ベイラー研究所移植部長のDr. Göran Klintmalmや、Dr. Marlon Levyをはじめとする移植チームは、寛容に受け入れてくださいました。移植外科チームが多国籍の外科医から構成されていることは、大らかな文化の礎の1つになっていたと回想します。Dr. Klintmalmはスウェーデン、Dr. Levyはフランス、細胞加工施設の部長のDr. Nazirrudinはインド出身と、実に多様でした。また、ベイラー大学病院の移植部門には、丸橋繁先生(現福島県立医科大学肝胆膵・移植外科講座教授)ら、日本出身の医師がフェローとして活躍されていた背景があり、移植スタッフは皆、温かく迎え入れてくださいました。
私は、同種膵島移植のための膵島単離に従事するほかに、第I・II相臨床試験に関する倫理審査や監査への対応も担当しました。留学初期は、訛りがある英語が分からず何度も聞き返すことを繰り返していましたが、2年程度経過するとようやく、耳が慣れてくるようになりました。この過程では、実に多くの専門家と出会いました。診療現場の医師、看護師(治験コーディネーターを含む)、薬剤師はもちろん、統計家、知財戦略担当者、倫理委員会、保険会社と交渉する医事課、データマネジメントチーム、研究資金を扱う事務スタッフ。膵島の単離を行う細胞加工施設(CPC)では、ラボマネージャーや品質保証担当者、設備管理者も重要な役割を担いました。さらに、安全性モニタリング委員会(DSMB)では、外部の医療機関に所属し膵島移植に従事する医師が客観的に評価を行いました。
新規臨床試験を開始するための申請(Investigational New Drug Application:IND申請)も経験させていただきました。規制省庁であるFDA(Food and Drug Administration)に勤務経験のある先生にご指導いただきながら研究計画書や申請文書を整備した経験や、実際のFDAとのやり取りは、日本に帰国後に、神奈川県立がんセンターで臨床試験を担当する部署に勤務した際にも大いに役立ちました。

倫理審査・FDA申請を通じて培った経験
このような審査手続きとは別に、臨床試験の遂行には被験者へのアプローチも欠かせません。被験者募集に関しては、今でも印象に残る出来事があります。ある日、学会から戻った私に事務スタッフが「膵島移植を説明する動画を撮影したいので、病院の地下に来てほしい」と声を掛けてきました。病院の地下に何があるのかと半信半疑で地下に行ってみると、何と、動画撮影用のスタジオがあり、プロンプター(原稿を投影する装置)まで揃っていました。実際の撮影では、緊張してしまい、一方で、プロンプターで原稿が次々に流れるため、説明中に何度も詰まってしまうことが多発し、動画編集のスタッフには大変苦労を掛けました。
Youtubeの動画は不特定多数の方への一方向型の情報発信ですが、地域住民を対象とした寄付活動にも参加しました。寄付のための研究説明会では、住民の方からの質問も受付け、臨床試験の意義を改めて考え直す良い機会となりました。私は、JDRFという小児糖尿病の患者団体からの研究資金を得ていましたが、競争的研究資金の獲得のほかに、このような住民からの寄付金も研究活動に充てられました。
東日本大震災と米国からの支援活動
こうして研究どっぷりの生活を過ごしていたところに、2011年3月11日の朝、東日本大震災の一報が入りました。その時目にしたニュース映像に、私は言葉を失いました。しかし、さらに驚くべきことには、東日本大震災の発災当日からベイラー大学病院を中心とした医療機関グループが支援に動き出したのです。数日後には義援金と、40フィートのコンテナ満載の救援物資が集まりました。まだ、被災地が寒い季節だったということもあり、医療物資のみならず、防寒着も多く集まりました。輸送を担当することになった私は、検疫や税関の手続き、国際輸送の実務に追われました。輸出入の手続きなど全く素人ながら、石巻赤十字病院、南相馬市立病院、鹿島総合病院、大町病院などへ実際に訪問しながら物資を届けました。支援物資を被災地を届けられたのも多くの方々の協力があったからこそで、関係者には心から感謝しております。
そして、病院グループ一体となった被災地支援で中心的な役割を果たしたのが「Faith in Action Initiatives」のメンバーでした。この活動は、主に大学病院の Spiritual Care部門が担っていました。留学前から“スピリチュアル・ケア”という言葉は知っていましたが、実際にどのように診療に関わっているのか想像できていませんでした。単に、精神的ケアの一環として考えていなかったのです。
被災地支援プロジェクトで、しばしばSpiritual Care部門のスタッフとミーティングを行ううちに、同部門のスタッフの顔を識別できるようになりました。その後、彼らが病院内の礼拝室のみならず、入院病棟やICU、外来で患者さんと対話している光景を目にするようになり、その活動の広さを実感しました。Spiritual Care部門が幅広く活動していた背景に、ベイラー大学病院がバプテスト教会の療養所を発祥としていることも関係していました。

テキサスバーベキューと留学を振り返って
テキサスはバーベキュー発祥の地とも言われます。留学前は、バーベキューといえば野外で肉を焼く程度の認識でしたが、実際には前日からじっくり燻製にし、食べる直前に焼き上げます。長時間の燻製は保存食としての歴史を持ち、今では人々が集い、笑顔を交わす象徴的な食文化となっています。仲間と囲んだテキサスバーベキューの味は、心を和ませてくれる大切な記憶です。近年、臨床研修制度の変化や米国の政情、円安の影響もあり、留学者は減少傾向と聞きました。しかし、留学は医師にとって技術の習得だけでなく、人と社会に向き合い成長する貴重な機会です。私にとって留学経験は、まさに長く燻されて旨味を増すバーベキューのように、日々の診療を支える糧となっています。


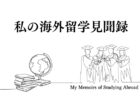
LEAVE A REPLY