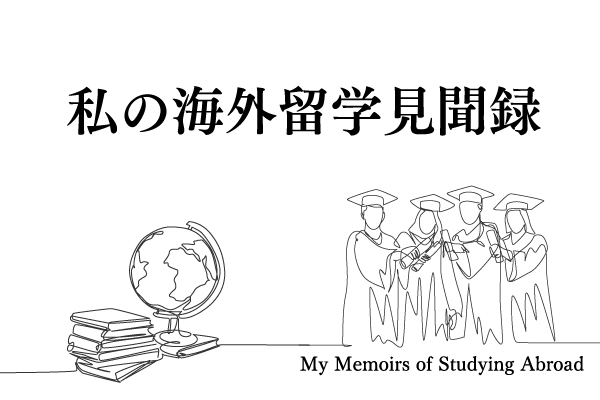
中村 真樹 (なかむら・まさき)
NTT東日本関東病院泌尿器科部長 骨盤臓器脱センター長
留学先: Karolinska Institutet(Stockholm, Sweden) (2011年9月〜17年3月)
留学までの経緯
私は2001年に大学を卒業し、直ちに泌尿器科に入局。幾つかの関連病院で泌尿器科臨床を学んだ後、07年から東京大学大学院医学系研究科外科学専攻へ進学しました。大学院では恩師である前NTT東日本関東病院院長の亀山周二先生のご紹介で、東京大学医科学研究所細胞療法分野の北村俊雄教授にお世話になり、TGF-betaという細胞内シグナル伝達物質の研究を通して、遺伝子クローニング、プラスミド作成、細胞形質転換等の基礎技術を勉強させて頂きました。この頃は、いつかは留学したいという希望と、もう少し臨床に近い研究がしたいという気持ちを持っていましたが、ちょうどKarolinska Institutet に留学されている先生から日本人の募集が出ていることを聞き、応募しました。それが大学院3年生の初めで、卒業後にポスドクとして研究できる許可を頂き、留学が実現しました。
留学先での研究
スウェーデンの首都、ストックホルムにあるKarolinska Institutetは1810年に設立された歴史ある研究所で、世界的にはノーベル生理学・医学賞の選考委員会が置かれていることでも有名です。私は、Department of Microbiology, Tumor and Cell Biologyに留学し、Tumor angiogenesisについて研究させて頂きました。抗VEGF抗体への耐性獲得機序が主なテーマでしたが、マウスの褐色脂肪の研究 (Dr. Seki)や、Zebrafishを用いたCircadian rhythmの研究 (Dr. Jensen)にも関わることができました。大学院時代に学んだ遺伝子導入技術を用いて同僚の研究のサポートデータを作ることができたのは素直に嬉しく思いました。
2年間の予定で留学しましたが、2年目終了時に応募した研究に対してCancerfonden(スウェーデンがん協会)から3年間の生活費と研究費(年間約70万スウェーデンクローナ)が支給されることになり、留学が延長できることになりました。お給料として頂けるのは、このうちのごく一部でしたが、なんとか生きていける金額を頂けたのは有り難いことでした。当時の東京大学大学院泌尿器外科学教授の本間之夫先生には無理なお願いをお聞き入れ頂き、感謝しております。
研究室にはスウェーデン、ドイツ、イタリア、デンマーク、中国、キプロス、スイスなど多くの国から研究者が集まっていました。研究には辛いことも多くありましたが、同時期に留学していた日本人と励まし合いながら、全5年の留学を終え、17年に帰国しました。

ストックホルムでの生活について
ストックホルムは北緯59度に位置するため、夏至の日の出/日の入りは3時半/22時、冬至は9時/15時と極端に変化します。比較的、雪は少ないのですが−20℃になることもよくありました。タイヤをスパイクタイヤに変え、街路樹の霧氷やダイヤモンドダストを見ながら、凍った道を研究所まで通いました。子供にはスキーウェアを二重に着せ、時には橇に乗せて幼稚園に送りました。しかし本当に辛いのは寒さよりも暗さでした。実際、うつ病やアルコール依存症になる人が多く社会問題になっており、酒類は国営の酒店でIDを見せないと買えませんでした。
一方で夏は素晴らしく、気温は20〜25℃、短いけれど湿度の低い夏を楽しみました。スウェーデン人にとっては、4〜5週間夏休みを取り、海外や無人島にある別荘に行くというのが標準の過ごし方のようでした。医者も夏休みを取りますので、その間、病院ではがん治療も受けられなくなります。患者もそれを当然のものと受け入れているのは印象的でした。
高税率高福祉国家のため、生活費はある程度かさみました。EU諸国から輸入される野菜やデンマークの肉が中心でしたが、日本食材店も有りました。一方、幼稚園は無料でしたので、子供を連れての留学がしやすい国と言えるのではないでしょうか。
家族で留学するということ
私は妻と1歳の子供と3人で渡瑞しました。子供が幼少ということもあり、小学校入学の必要もなく良いタイミングだったかもしれません。研究室で研究することはもちろんですが、家族が安心して生活できる環境を作ることは何よりも大切です。
ストックホルムにはWenner-Gren財団という研究者をサポートしてくれる財団があり、Wenner-Gren Centerというポスドク用の格安アパートメントがあります。約80平米のアパートに2年間住むことができますので、ストックホルムで研究される方は早めに応募することをお勧めします。
私は留学決定時に申し込んだため、留学開始時に入居することができ、安全な環境で家族との生活を始めることができました。その後の住居選びはそれなりに苦労しましたが、何とかなるものです。
研究室での会話については英語が公用語ですが、行政とのやりとりにはスウェーデン語が必要でした。子育てしながら語学学校に通い、日常会話レベルまで上達した妻には頭があがりません。現在でも時々キッチンからスウェーデン語のラジオが聞こえてきますが、私には全く理解できません。ただスウェーデン人は子供も大人も英語が堪能です。日常会話レベルの英語ができれば、それほど困らないのではないでしょうか。
5年間の留学中に子供が2人生まれて3人になり、それぞれスウェーデンに因んだ名前を付けました。子供たちはみな自然豊かなストックホルムの幼稚園で学び、週末は家族で公園などに出かけました。日本人研究者も多く、家族ぐるみの付き合いもできました。慣れない環境で妻には多大な苦労をかけてしまいましたが、幼少期の子供たちと海外で一緒に暮らせたことは人生の中で掛け替えのない幸せな時間になりました。家族には“ありがとう”の気持ちで一杯です。
海外留学の意義について
先日泌尿器科の同門会で「若いうちに海外留学し、外国の文化や考え方に触れるのは大切な経験だ」というお話を伺いました。良きにつけ悪しきにつけ、我々の常識が通用しないことが海外では起こります。また、色々な国の人と付き合っていると、それぞれの歴史認識、他国への感情のようなものが垣間見えることもあります。一方、政治や国の立場に関係なく、個人としての親密な交流はできます。この経験はその後の人生のどこかで活きてきます。若い先生方にはぜひ2年以上の留学をお勧めします。
最後に
こうして留学生活を振り返ると、あの時しかできなかった経験だと再認識しています。そして、私の留学は多くの人に支えられて実現したものでした。留学を許してくださった教授、留学中ご迷惑をおかけした先輩方や同僚、後輩。妻や現地で元気に成長してくれた子供たちと両親と義両親や友人たち。全ての方々に感謝申し上げます。私の経験が留学を考えている方々の参考になれば幸いです。

Wenner-Gren Center中庭にて


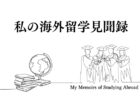
LEAVE A REPLY