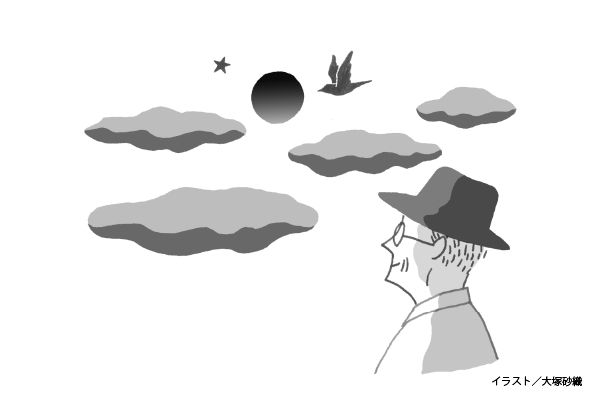
へき地診療医になって1年。毎日が学びの連続だ。
日本の多くの地域と同じく、私がいる北海道むかわ町穂別も高齢化率が凄まじい。19床ある病棟のほとんどは90代の入院患者さんで埋め尽くされ、たまに80代が入院となると看護師たちは「随分若い人ですね」と真顔で言うくらいだ。
昨年まで勤務していた医療機関の精神科の通院患者にも80代、90代の方はいたが、比率としては極僅かだった。それに比べるといま診ている患者の9割は80代、90代(さらには100歳以上)の超高齢者なのだから、私の診療環境は完全に逆転したと言える。
さて、はじめての超高齢者診療でいちばんむずかしいのは、「ガイドラインに沿った検査、投薬などの治療をどこまで進めるか」だ。精神科から総合診療科に転科したての私は、検査にしてもその結果を見るにしても処方にしても、基本はその疾患のガイドラインや教科書頼みになる。例えば2型糖尿病の場合、ヘモグロビンA1cが7.5%以上ならメトホルミンともう1種、別の作用機序の薬を処方する。その後であるが、教科書には「2剤治療3カ月間でヘモグロビンA1cが目標値に達しない場合は3剤治療へ」とある。
この「目標値」も年齢によって変わってくるわけだが、80代、90代で緩めに目標値を設定しても中々それを下回らない場合、どうするか。
実際に80代後半の患者さんに教科書の該当箇所を示しながら、「どうしますかね。ほら、ここにはお薬が3種必要と書いてありますが、新しい薬を追加していいですか」と伝えて、ハナで笑われたことがある。
「先生、オレの場合、こんなもんじゃないの。今から人生が始まるわけじゃないし、もうクスリは増やしたくないな」
そう言われたら返す言葉もない。私は「じゃあ、まあ運動と食事ですかね」と食事療法のパンフレットをわたそうとしたが、それも「先生、後何年生きてるんだか分からないんだから、好きなものくらい食べさせてよ」と笑顔で断られた。
亡父の最期を振り返る
その人との遣り取りで、私はもう10年以上も前の自分の体験を思い出した。私の亡父が敗血症に陥り入院したときのことだ。抗生剤の効果がなく意識状態も悪くなり、このまま人生を閉じることになりそうだ、と娘の私にも分かった。当時は泊まり込みでの付き添いも出来たので、心労から寝込んでしまった母親の代わりに私がその役を担った。あるとき、訪室した看護師が、中心静脈からの高カロリー輸液で命をつないでいる父親のルートから何かを静注しようとした。実は父の入院先は、私が20代後半の一時期、勤務したことがある医療機関だった。私が「何を入れるの?」と訊くと、お互いの若き日にいっしょに働いたことのある看護師は、気軽に教えてくれた。「血糖値が上がりすぎちゃったからインシュリンでコントロールすることになったの」
私は少なからず驚いた。父は膵臓の良性腫瘍の手術歴はあるが、幸いにして術後、糖尿病にはならなかった。糖尿病の既往がなくても中心静脈栄養の場合、血糖の上昇が起きるということも当時の私は知らなかったので、まずそのことに驚いた。そして、人為的に入れたグルコースで起きた高血糖をインシュリンの静注で下げる、というプロトコルがあることも知らず、それにも少なからず驚きを覚えた。
その情景を見ながら、私は考え込んでしまった。父はもうおそらく回復不能だろう。だとすると、今はいわゆる「延命治療」の段階に入っていると言える。そのために高カロリー輸液を行い、さらに血糖が上がりすぎたからといってインシュリンを使う。そのことに意味があるのだろうか……。それから私は、家に居る母や他の家族にもそのことを説明し、「こんな風に命を長引かせられるのは決して父親らしくないと思う」と伝えた。するとみな「その通りだ」と同意してくれ、翌日、父親を自宅に連れ帰って看取ることが出来たのだ。もちろん、先ほどの80代の外来患者さんは死の床にあった父親とは違う。血糖降下剤を2種から3種にすれば効果が出て、心血管イベントなどのリスクは下がるかもしれない。ただ、「今から人生が始まるわけじゃないし、もう厳密なコントロールはいいよ」と言うその人の気持ちもよく分かる。私も正に、父親のときに「もう人生が終わろうとしてるんだし、もう厳密なコントロールはいいよ」と思い、院内の取り決めでそれを行わなければならない医療にある意味の“見切り”をつけて、自宅で看取ろうと心を決めることが出来たからだ。もし、あのとき顔見知りの看護師が「これはインシュリン」と教えてくれなければ、私はそれも出来ずにそのまま父の命が病院で潰えるのを待っていたであろう。
患者を見捨てない診察と処方
医療で難しいのは、「全ては事後的にしか分からない」ということだ。例えば、先の80代の患者さんに「よし、じゃあちょっと数値は高いけど、薬を増やすのは止めましょうか」と言って、その後、その人が心筋梗塞で亡くなったとしよう。家族も私も「あのとき本人を説得して薬を増やし、糖尿病のコントロールをしっかりやっておけば」と思うかもしれないが、とは言え、もし薬の効果でコントロールが良好なら心血管イベントは起きなかったか、というとそうも言い切れない。その場合、家族は「こんなに早く亡くなるなら、嫌がる薬を無理やり沢山飲ませないで、もっと自由に過ごさせてあげればよかった」と思うに違いない。高齢者への薬の出し方についての座談会を読んでいたら、ベテラン医師がこう発言していた。
「薬を飲んでいたのに病気になることもあれば、飲んでいなくても病気にならない場合もあるわけです」
本当にその通りだ。しかし、これでは余りに身も蓋もなく、患者や家族も「そんなことは私にも分かりますよ。専門家としての意見を聞かせて下さい」と言うに違いない。同じ座談会で別の医師はこう言っていた。
「『生きるか死ぬか』より『元気で居られるかどうか』を優先する方も多いです」
これなら未だ分かる。その為にはまず転倒リスクのある薬、転倒したときに出血の恐れがある薬を減らす、などの方針が立てやすい。ただ、先ほどの糖尿病の患者さんの場合、「元気で居られるかどうか」よりもさらなる優先順位として、「楽しく自分の好きなように暮らせるか」があるのだと思う。多少、命が短くなっても、多少、元気で居られない時間が長くなっても、それまでの間、色々と我慢したり飲みたくない薬を無理に飲んだりするよりは、思い切り自分らしく生きたい。それは極めて真っ当な願いであり、それに対して医者が免責の為に「死んでもいいんですね」「人工透析になっちゃっても知りませんよ」などと脅し文句を口にすることはあってはならないだろう。もちろん、「じゃあ、受診してもしょうがないですね。責任が持てないのでもう来ないでください」も間違っている。
決して患者を見捨てることなく、その人の人生の質やその人らしさを十分に保てるようにするには、どのような治療を行うのが最善なのか。へき地の診療所で日々、考えさせられている。




LEAVE A REPLY