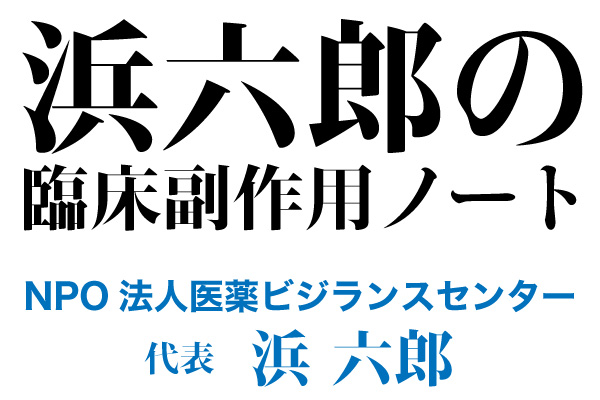
今回は、慢性閉塞性肺疾患(COPD)の患者にセロトニン再取り込み阻害剤(SRI)やベンラファキシンなどのセロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤(SNRI)を服用している患者で、肺炎やCOPD悪化が増えることを示した調査結果について、薬のチェック118号1)で取り上げたので概略を紹介する。
大規模コホート研究法で関連あり
調査は2つある。1つはSRI/SNRI使用者29,835人、非使用者88,776人から、年齢、罹患年数、過去の処方薬剤、入院頻度、既往歴、ベンゾジアゼピン剤使用歴、禁煙用薬剤の使用など、合計40項目の交絡因子で傾向スコアをマッチさせた両群28,360人ずつを選び、90日間のイベントを比較した大規模コホート研究である。
危険度(ハザード比)は、肺炎による入院1.15(95%信頼区間、以下省略:1.05,1.25)、肺炎/COPD死亡1.26(1.03,1.55)、総死亡1.20(1.11,1.29,p<0.0001)であった。特に、精神関係疾患の既往歴のない人では、肺炎による入院1.3倍、ICU入院1.8倍、肺炎/COPD死亡1.8倍、総死亡1.7倍と顕著であった。
自己対照ケースシリーズでも関連あり
もう1つの調査は、40歳以上(平均65歳)の新規に診断されたCOPDで、診断前1年間のデータがあり、抗うつ剤の処方記録がある31,253人の患者を対象にした自己対照ケースシリーズ法による研究である。
患者自身の抗うつ剤を使用していない時期を対照として、抗うつ剤を使用開始後90日間の肺炎発症あるいはCOPDの悪化を比較した。自己対照なので、交絡因子に大きな問題はない。
肺炎の罹患率比(IRR)は1.8(1.5−2.1)、COPD悪化は1.15(1.11−1.20)であった。これらIRRの増加の程度は、SRIとSNRIで同程度であった。
三環系抗うつ剤でも肺炎のIRRが1.6(1.4−2.0)、COPD悪化が1.16(1.11−1.21)と増加していた。
抗うつ剤の免疫抑制作用が関係
抗うつ剤で肺炎が増加するメカニズムとして、各種あげられているが、SRI/SNRIの抗炎症作用や免疫抑制作用との関連が、特に重要と考えられる。肺炎死亡だけでなく、総死亡も増えているからである。
免疫抑制作用との関連は、動物実験で裏付けられている。例えば、指標によってはSRIのほうがデキサメタゾン(強力なステロイド剤)よりも免疫抑制力が強いとか、動物で臓器移植の拒絶反応を抑制した、あるいは、大腸菌の感染実験では、ヒト使用量(体表面換算)のSRIで感染巣の病変が増強したなどの実験結果で裏付けられている。
そもそも、SRI/SNRIのうつ病に対する効果に抗炎症作用が関係していることは多くの文献で主張されていることである。
したがって、この免疫抑制作用、抗炎症作用が感染症を増悪させるメカニズムとしても働くことは、もはや疑いがない。
抗うつ剤の処方よりも呼吸モニタリングを
COPD患者の血中酸素濃度は低下しており、低酸素血症が続くと組織に損傷が生じ、修復のために炎症が起こる。硬膜の炎症で頭痛が生じ、脳内の炎症は不安やうつ病の原因になる。
COPD患者の頭痛や不安、うつ状態には、抗うつ剤を処方するよりも、より綿密に呼吸状態をモニタリングして、精神科系薬剤を含めて、呼吸状態を悪化させる薬剤(睡眠剤など)が処方されていないか、その影響で呼吸状態が悪化していないかを検討する必要がある。


LEAVE A REPLY