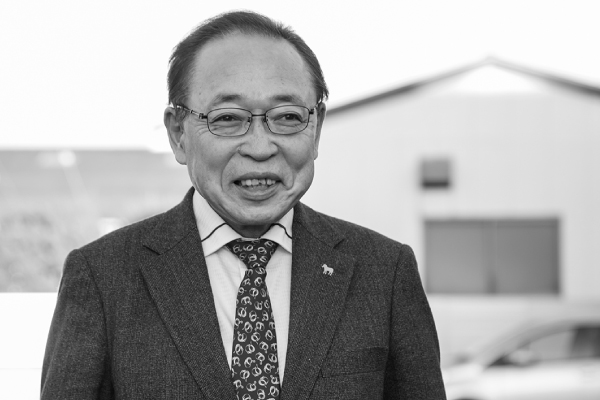
消化器外科医
療養型病院勤務
片山 隆市/㊤
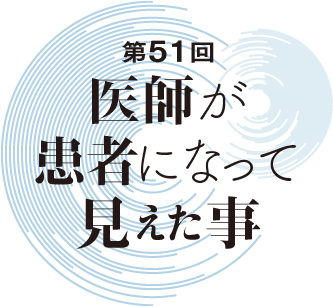 医学部を出て40年、自ら“病気のデパート”と苦笑するほど、心身の病に苦しみながら、なお、医師の職責を全うしている。 最初は28歳でのがん宣告だった。
医学部を出て40年、自ら“病気のデパート”と苦笑するほど、心身の病に苦しみながら、なお、医師の職責を全うしている。 最初は28歳でのがん宣告だった。
ヒマラヤから下山途中に大量吐血
1980年5月、ヒマラヤ山脈の麓の町、ネパールのポカラだった。東京慈恵会医科大学を卒業し、当時は4月に実施されていた医師国家試験を終え、発表を待つまでの長い春休み。母校の先輩とともに、アンナプルナ連峰のグサン・ピーク(6200m)登頂を成し遂げて、祝杯を挙げた。
翌早朝、強い嘔気を感じた。胸元から突き上げてきた吐瀉物は、赤いゼリー状の塊だった。最後に食べたのはデザートのアップルパイで、黄色いはずだった……。突然のことに動転した。それは大量の吐血だったが、理解できなかった。医師の卵にとって、吐血とは流れる血を吐くことだと了解していたからだ。目の前は真っ白で、ふらふらとその場に倒れ込んだ。トイレに目覚めると、便は真っ黒のタール状だった。
同行した先輩は脳外科の研修医で、事態を把握し切れていなかったものの、非常用に持参していたリンゲル液500mlを点滴してくれた。幸い片山は血の気を取り戻し、気分も軽快して下山し、経由地のバンコクに辿り着くと、中華料理店でビールを飲み干して無事を祝い、何事もなかったかのように帰国した。
晴れて医師となり、5月末から国立東京第二病院(現・独立行政法人国立病院機構東京医療センター)で、一般外科医としての修業が始まった。ヒマラヤでの出来事は誰にも告げていなかったが、心の中に引っかかっており、患者として消化器内科を受診した。内視鏡検査に加え、出血したとおぼしき場所から細胞を採取して調べるバイオプシーが行われた。病理医は、良性から悪性まで5段階でグレードを付け、さらにaとbを組み合わせて診断する。片山の組織は「クラスⅢb」、真ん中よりわずかに悪性寄りの境界線上だったが、肉眼的には胃潰瘍との診断が下された。
翌月に再度検査を受けるように言われ、受診した。昼となく夜となく病院で過ごし、吸収することは多かった。加えて、夜は新人歓迎の宴会が続いた。何ら自覚症状はなく、忙しさにかまけ、片山は結果を聞きに行かず放置していた。折悪しく、診断した消化器内科医も学会などで多忙を極め、検査結果は片山に伝えられる事なく、誰の目にも触れずカルテに挟まれたままだった。
半年が過ぎた。1981年が明けて早々、早稲田大学山岳部がその夏、カラコルム山脈のK2(8611m)登頂を計画しており、同行する医師として片山に打診があった。同大学山岳部関係者との顔合わせも済ませて、胸が高鳴っていた。
ヒマラヤでの吐血の経験から、念のため今一度検査を受けることにした。今度は、バリウムを飲んでのX線透視検査だった。東京第二病院の検査室には、物見遊山半分で同期の研修医たちが集まってきた。しかし、検査は始まらず騒然としていた。片山のカルテが開かれてみると、挟まれていた6月の検査結果は「クラスⅤ」、つまりまごう事なき悪性という診断があったのだ。その1月前の5月には「Ⅲb」。消化器医長から結果を伝えられた片山も愕然とした。X線検査の結果は、がんの診断にダメ出しをするものだった。
〝神の手〟を持つ大御所の手術を受ける
外科医長に「すぐに手術を受けなくてはダメだよ」と諭された。多分早期がんだろうが、手術したら好きなお酒は飲めなくなるかもしれない。片山は動揺しながらも、どこか冷めていた。
「なるようになるだろう。手術さえ成功すれば、治って助かるはずだ」。学閥などのしがらみを避けるため、当時の癌研究会附属病院(東京都豊島区)で手術を受けることになった。蓋を開けると、執刀医は、院長の梶谷鐶と決められていた。もう72歳になっていたが、“神の手”を持つ伝説の名医だった。“まな板の上の鯉”になるしかないと、覚悟を決めた。診断は、印環細胞がんという、胃がん全体の10%を占めるたちの悪いがんだ。胃粘膜の表に現れず、胃壁の中を這うように広がっていくため、発見が難しい。しかも進行が早く、粘膜下層まで浸潤すると、極めて予後の悪いスキルスがんの母地となる。リンパ節にも高確率で転移し、予断を許さない。
手術を前に、あれこれと来し方の思い出が去来した。片山は1952年、東京都江戸川区に生まれた。母子ともに命を危ぶまれた難産で、産声も上げず仮死状態で生誕したが、その後は大過なく育っていた。その母は助産師で、父は自動車の部品商を営んでいた。片山は弟に家業を譲り、自分は好きな道を歩ませてもらうことにした。東京都立両国高等学校を卒業し、立教大学理学部物理学科に入学したが、物理学で身を立てるのは難しいと早々に見切りを付けた。当時は医師不足の時代で、人助けをしようと、仮面浪人して受験勉強に打ち込み、慈恵医大に合格した。
登山への関心が芽生えたのは高校時代だったが、もっぱら1人歩きで、本格的に打ち込んだのは、慈恵医大の山岳部に入ってからだ。かつては総合大学のそれに肉迫するほどレベルが高かった。のめり込む物を見つけ、体力はもちろん、忍耐力や持久力も身についた。1つ間違えば命取りになるため、“兵站術”にも細心の気配りが必要である。
6年生の夏休みは1カ月かけて、ヨーロッパの山々を巡った。それから国試の準備に集中したが、同級生より遅れていることで焦りもあった。夜中にキリキリと胃が痛んだ。振り返ってみると、それが胃がんの前兆ではなかったか。
片山の手術は開腹で行われ、胃の5分の4を切除した。これまで虫垂炎や鼻中隔弯曲症の手術を受けたが、全身麻酔の本格的な手術は始めてだった。「取り切れた」との判断だったが、手術後も吻合部から大量出血があった。足取りも覚束なかったが、手術から17日目に退院した。残胃の内容物が急速に小腸に流入し、一度にたくさん食べられない。食後はダンピング症候群で動悸、めまい、下痢……など、様々な症状が出て数年間苦しめられた。逆流性食道炎もあった。逆流するのは胃酸でなくアルカリ性の腸液で、喉も荒れた。
体重は5kgほど落ちたが、半年もすると元の体重に戻ってきた。危機は去ったようだ。「スキルス胃がんに進んでから見つかったら、命取りになっていたし、むしろ幸いだった」。落ち込んだ気持ちも回復していった。
4年後には、今度は癌研病院に入職し、執刀してくれた梶谷から直々に指導を受けることもできた。その後は、母校に戻る予定で、医長としての激務が待ち構えていたが、結果的にそれが片山の人生に大きな陰を落とすことになった。(敬称略)
(聞き手・構成)ジャーナリスト:塚嵜 朝子




LEAVE A REPLY