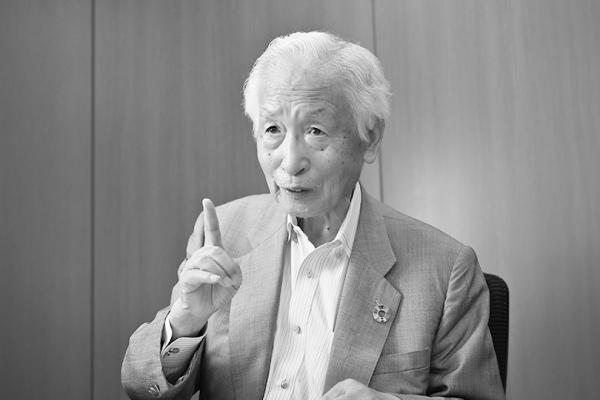
国政選挙で自民党の敗北が続き、連立政権が苦境に立たされている。海外ではロシアによるウクライナ侵攻が続き、米国トランプ政権との関税交渉も一応の決着を見たと言っても、不透明な部分が多い。国内も少数与党政権で、物事が決まらない事態が続いている。最近は新興政党への支持が高まっているが、これも国民が難局を打破する為、新たなリーダーを求めている証左だろう。今の日本で、どの様な政治家が求められているのだろうか。嘗て、故・田中角栄首相の秘書官として、政治の現場を官僚の立場から見て来た元通商産業省(現・経済産業省)事務次官で、弁護士の小長啓一氏に田中氏の政治姿勢やリーダーに求められる資質等を聞いた。
——通産官僚の道を選ばれたのは、どの様な理由からだったのですか。
小長 私は13歳の時に大阪陸軍幼年学校に入り、将来は将校となってお国に尽くすつもりでしたが、終戦を迎えて故郷に戻り、旧制西大寺中学(現・西大寺高校)を経て旧制第六高等学校へ進学しました。1949年の学制改革で発足した新制岡山大学に第1期生として入学し、在学中に国家公務員上級職(法律職)試験と旧司法試験に合格しました。元々、卒業後は役人となり行政に携わりたいという思いが有りましたが、父親は学校の教員であり、大学では先輩の伝手も無く、国の省庁の実際の業務について深い知識が有った訳ではありません。そうした時に、大学の恩師から「通商産業省(当時)は世の中や世界の動向に機敏に対応し、比較的自由な雰囲気が有る。中央官庁を目指すのなら通産省が良いのではないか」と言われた事が有り、そうした役所であれば受験してみようと思ったのです。
——試験にはどの様に臨まれたのですか?
小長 面接では試験官が受験生を取り囲み、議論をする様な印象でした。そこで「何故通産省を受験したのか」と尋ねられ、「資源に乏しい日本は、製品の付加価値を高め、貿易で稼いでいくしか生きる道は無い。その使命を担う通産省で学び、力を尽くしたい」という趣旨の話をしました。専門家を前に、臆する事無く堂々と語ったのが試験官の琴線に触れた様です。既に司法試験には合格していましたから、駄目でも弁護士の道が有る、と比較的気楽に試験に臨めたのも、結果的には良かったのかも知れません。
——故・田中角栄氏の通産大臣(当時)時代から首相時代まで秘書官を務められました。
小長 田中氏が通産相に就任したのは71年の第3次佐藤(栄作)改造内閣の時です。前任の宮澤喜一氏は田中氏より年下であった為、次の大臣が宮澤氏より年長であれば、秘書官も現職より年長の私が候補になる事になっていました。候補者は私を含め3人程いましたが、官邸から田中氏の就任が決まったとの一報が有り、私が省幹部と共に挨拶に行く事になりました。この時が初対面でしたが、当時、田中氏は既に郵政大臣(現・総務大臣)や大蔵大臣(現・財務大臣)、自由民主党の政調会長、幹事長等を歴任していた大物ですから、「この様な人の秘書官が自分に務まるのか」と緊張した事を覚えています。幹部が私の事を紹介すると、田中氏は「通産省が決めた事に何の異存も無い」とだけ言い、それで秘書官就任が決まりました。
政治決断を目の当たりにした秘書官時代
——田中氏が通産相になって先ず取り組んだのが、日米繊維交渉でした。
小長 この交渉は、それ以前にも大平正芳氏や宮澤氏の両通産相(当時)が担当しましたが、何れも合意には至りませんでした。田中氏は交渉時の迫力が前任の2人とは段違いでしたが、それでも、最初の協議は物別れに終わった。すると、今度は官僚に向かって「俺は君達の方針に従って話したが、事態は少しも改善しない。このままで良いのか」と檄を飛ばしたのです。当然、次官以下の官僚も方針の見直しを考えざるを得なくなりました。
——官僚が自ら方針を転換する様に持っていった。
小長 そこで幾つかの代替案が検討されましたが、田中氏が提示したのは、「米国向け繊維の輸出増を抑える代わりに、国内事業者の損失を政府が補償する」という案でした。損失額を試算すると総額は約2000億円に上り、通産省予算の半分に相当します。流石に繊維業界の為だけに予算の半分を割く訳にはいかず、「大臣、それでは巨額過ぎて実現困難です」と答えるしかありません。ところが田中氏は、「業界に現金を渡すのではない。廃棄される設備を2000億円分買い上げる。この案に産業政策上の問題が有るか」と次官に尋ねたのです。次官が「問題有りません」と答えると「分かった。2000億円の事は俺に任せろ」と言い、更に私に「今から佐藤総理に電話してくれ」と命じました。かくして直談判に至り、細部に亘るやり取りは有りましたが、総理から了承を取り付けたのです。




LEAVE A REPLY