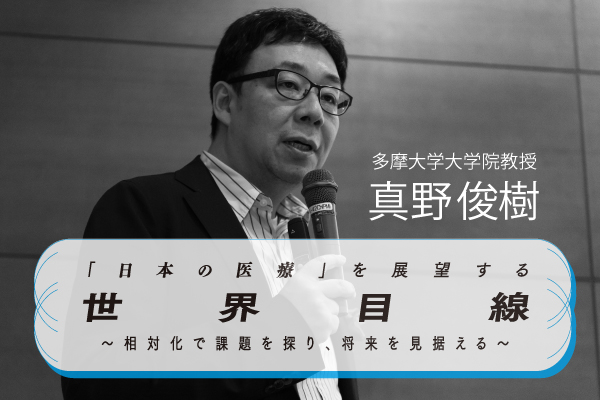
医療ツーリズムのさらなる展開
前号でも触れた通り、昨今、医療ツーリズムは再び注目を集めている。そこで、前稿ではその定義や発展の背景を振り返りつつ、世界的な市場拡大やアジア諸国の成長戦略に焦点を当てた。高度な治療を求める富裕層、迅速な医療を望む患者、さらには観光を兼ねた予防医療の利用者など、多様なニーズに応えるかたちで、医療ツーリズムは今や世界規模の産業となっている。今回はこの流れを踏まえ、各国がどのような制度や政策を通じて医療ツーリズムを推進しているのか、具体的な比較を試みたい。
医療ツーリズムの国際的な現状
世界全体の傾向として、医療ツーリズムの受け入れ競争は年々激化しており、多くの国が専門部署を設けたり、国策として振興策を講じたりしている。現在では50カ国以上で組織的な医療ツーリズムが展開されており、アジア・中東・欧米を中心に年間延べ1500〜2000万人規模の患者が国境を越えて治療を受けていると言われる。
特にアジア地域は世界の医療ツーリズム市場の中核とも言え、タイ、シンガポール、マレーシア、インド、韓国などは、国家として「医療ハブ」戦略を掲げ、海外患者誘致にしのぎを削っている。
アジア各国の多くは、政府主導でJCI(Joint Commission International)という病院の運営基準に関する国際認証の取得を奨励し、専門のエージェントや優遇ビザ制度を整備するなど、官民挙げた取り組みを展開してきた。その結果、タイやシンガポールを筆頭に、アジアは世界最大の医療ツーリスト受け入れ地域へと進化した。例えばタイは、2010年代には年間200万〜250万人という世界最多クラスの外国人患者を受け入れている。シンガポールも70万〜100万人規模、マレーシアやインド、韓国も数十万〜100万人超の受け入れ実績がある。
これに対して日本の受け入れ数は、正確な数字は明らかではなく、別途調査に委ねるが、年間数千人から2〜3万人規模に留まっているとも言われる。また、日本におけるJCI認証の取得施設は約30病院前後で、近年その数は増えていない。この点も大きな違いと言えよう。
欧米の先進国に目を移すと、こちらも引き続き高度医療を求める患者の受け入れ先となっており、米国には中東や南米から年間数十万人規模の患者が訪れているとされる。ドイツやイギリスも、世界各国から富裕層患者を集めている。先進国・新興国それぞれの強みを生かした医療ツーリズムが展開されているこの状況は、もはや特筆すべきことではなく、通常の現象とも言えよう。
総括すると、タイやシンガポールなど東南アジアが費用とサービス面で強みを活かして圧倒的な患者数を獲得している一方、日本は本格的な受け入れはこれから伸ばそうとしている段階であることが分かる。一方、米国は高度先進医療の提供国として特別な地位を占めつつ、逆に自国民の海外流出も多いという送受両面の特徴があり、中国もいずれそうなると見られている。日本は技術力や衛生水準で定評があるが、市場規模や受け入れ体制は他国に比べまだ小さく、前向きにとらえれば、今後の伸び代が大きい段階であると言える。
医療ツーリズムの各国の制度・政策の比較
これまで見てきたように、世界の各国は、医療ツーリズム推進のために多様な制度・政策を導入している。主要国それぞれの国情に応じた取り組みと特長を下記にまとめ、俯瞰してみよう。
日本の制度・政策:日本政府は観光立国戦略の一環として医療ツーリズムを位置付け、11年に「医療滞在ビザ」制度を開始した。このビザにより、最長6カ月の長期滞在が可能となり、付添者の入国も認められている。しかし実際には、取得手続きの煩雑さや費用から利用者は限定的で、訪日医療患者の多くは短期滞在ビザ(観光ビザ)で入国しているのが実情である。
それでも医療滞在ビザの発給数は年々増加しており、19年には1653件まで伸長した。その内、約80%は中国からの申請である。日本では厚生労働省・経済産業省などが連携し、外国人患者受入体制整備事業を展開している。具体的には、厚労省の流れを汲むJMIP(https://jmip.jme.or.jp/)や、Medical Excellence Japan (MEJ) が主に経産省の委託で選定病院の国際診療対応力評価(認証制度)を行っており、かつMEJでは外国人患者紹介事業者の登録制(身元保証機関制度)を導入してブローカーの適正化を図っている。
JMIPは医療ツーリズムに限らず、日本国内の医療機関に対し、多言語による診療案内や、異文化・宗教に配慮した対応など、外国人患者の受入れに資する体制を第三者的に評価することを通じて、国内の医療機関を受診するすべての外国人に、安心・安全な医療サービスを提供できる体制づくりを支援している。さらに10年代からは、国費助成で通訳者養成や多言語対応ガイドライン整備も進められている。
とはいえ日本では病院の広告規制や営利制限があるため、タイのように民間病院が派手に海外宣伝するのは難しく、官主導で「日本の医療ブランド」発信に努めている段階といえよう。
中国の制度・政策:中国政府は自国民の医療ツーリズムによる海外流出を受け、10年代から国内で高度医療を受けられる環境整備に乗り出した。加えて、中国は医療仲介産業の育成にも熱心で、北京などには海外医療コーディネート会社が続々登場した。
著名な例として、日本にも支店がある北京圣露西亜(St. Lucia)国際医療が有り、11年の創業からわずか数年で年間数千人規模の患者を海外に送り出し、米国VCから800万ドルの出資を受けるなど急成長している。中国政府もこのような仲介業者を活用して海外医療機関との提携を進めており、中国版MEJともいえる公的な海外医療情報プラットフォーム構築も模索されている。
もっとも中国は国土が広大で国内格差も大きく、まずは国内医療体制の底上げが急務であるため、医療ツーリズム政策は地域限定の試行に留まっているともいえる。
タイの制度・政策:タイは政府と民間が一体となった医療ツーリズム推進の成功例である。1997年の通貨危機で経済打撃を受けた際、外貨獲得策として医療サービス輸出に注目し、2002年に「アジアの医療ハブ」構想を掲げた。以降、政府は外国人患者のビザ発給手続きの簡素化、空港の医療カウンター設置、医療通訳の育成支援などを次々に実施した。医療機関側も積極的に対応を強化しており、筆者も15年ほど前に何度か訪問したバンコクのバムルンラード病院では、年間52万人、190カ国以上の海外患者を受け入れる体制を整えている。同院では、150名超の専任通訳や外国人専用ラウンジ、空港・病院間の送迎サービスを備え、「空港に降り立った瞬間からVIP医療ツアー体験」を提供している。また病院自ら海外にマーケティングチームを派遣し、中東やロシアなど重点市場で患者誘致を展開している点も特長的といえよう。
タイ政府の推計では医療ツーリズム収入は年間数十億ドル以上に達し、観光を含めた経済波及効果も大きいとされている。制度面では、90日間滞在可能な医療観光ビザの発給、民間病院の外資出資規制緩和など、きめ細かい支援策で民間主導の成長を後押しした。結果としてタイは、東南アジア随一の医療ツーリズム大国となり、多くの国のモデルケースと見なされている。
次回は、米国の様子を詳説する。
参考資料
mediphone「医療ツーリズムの現状|世界・日本の状況や問題点を解説」2024年11月他 https://mediphone.jp/articles/medical-tourism
フロンティア・マネジメント「コロナ禍を経た『メディカルツーリズム』の行方」2022年9月他 https://frontier-eyes.online/medical-tourism/
日本政策投資銀行レポート 植村佳代「進む医療の国際化〜医療ツーリズムの動向〜」『総合健診医学』39巻6号, 2012
U.S. International Trade Commission, Medical Tourism 2015
Patients Beyond Borders Fourth Edition: Everybody's Guide to Affordable, World-Class Medical Travel Paperback – January 20, 2020 by Josef Woodman
How to evaluate surgical tourism service organizations in China: indicators system development and a pilot application 2022


LEAVE A REPLY