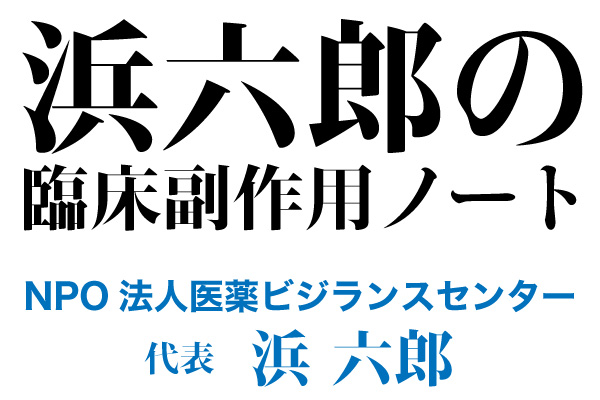
セロトニン再取り込み阻害剤(SRI)はいずれも胎児毒性が報告され、さらには出生直後の重篤な症状、持続性肺高血圧症が添付文書の妊婦への使用の注意事項として記載されている。しかし、パロキセチン(パキシル®)が人に使われる前に実施された動物実験で、しかもヒトに用いる最低用量相当でも、出生直後の死亡が増加すること、その安全量(無毒性量)は、毒性試験では決定されていないこと、雄のみの投与で不妊が生じることも動物実験で確認しておきながら、添付文書に記載していない。そこで、これらを分析したTIP誌の報告1)を翻訳して、薬のチェック英字版(MedCheck in English No33)2)に掲載した。その概略を紹介する。
新生児が4日以内に高率に死亡
動物実験で最も顕著な毒性は、新生児の死亡率の増加であった。ヒトでの常用量上限(1日40mg)に相当する4.3mg/kgでは新生児の69.1%が4日以内に死亡(対照群11.5%)した。ヒト常用量下限(10mg)に相当する1mg/kgでも18.5%(対照群6.1%)が4日までに死亡。4日以内の死亡は対照群に比しオッズ比3.49(95%CI:2.05-6.54、p<0.0001)であり、ヒト常用量相当レベルで動物の新生児死亡は確実に増加する。
親動物にも毒性、雄だけ投与でも不妊
親動物に用量依存性の有意な死亡、不交配、不交尾、不妊、流産(全吸収)、着床後胎児の死亡、胎児の低体重、新生児の死亡(4日以内、21日以内)を認めた。
雄のみが使用した場合でも不妊が増加した。雄では、精子数の減少や精子の運動性低下、精巣上体の腫大や膿瘍、精液瘤、精細管萎縮なども認められた。
器官形成期に使用した場合に骨格の変異が用量依存性に有意に増加した。
ヒト新生児の出生直後の重篤な症状
SRIを使用した母親から生まれたヒト新生児離脱症候群が1993年以降報告されている、パロキセチンが関係した新生児離脱症候群は97年に第1例が報告された。対照群を設けたコホート研究で、妊娠後期にパロキセチンを使用した場合22%の新生児に、けいれんを主とした離脱症候群が出現した(対照群5.6%)。呼吸窮迫のオッズ比は10.35(1.27-84.67)、調整オッズ比は9.53(1.14-79.3)であった。
症例対照研究により、SRIを用いない場合に比べた持続性肺高血圧の相対危険は、SRI全体で6.1倍、パロキセチンでは25倍であった。妊娠後期のSRIへの曝露は出生後の新生児に、易刺激性や呼吸窮迫、けいれんを中心とする離脱症状を高頻度に引き起こすことは確実である。
パロキセチン離脱の影響は、持続性の肺高血圧の危険を招き、心房中隔欠損や心室中隔欠損の自然閉鎖が阻害され永続的になる危険性がある。また、精神神経の行動発達に悪影響を及ぼす可能性が動物実験の結果からも具体的に懸念されている。
実地臨床では
妊娠中はもちろん、妊娠可能な女性にSRIは禁忌とすべきである(ただし、使用中なら減量のうえ中止)。添付文書の記載は不備である。出生直後の動物の死亡が臨床最小用量相当量で対照群の3倍超に起こり、安全量(無毒性量)が決定できていないこと、持続性肺高血圧症の危険度は6.1〜25倍であって、添付文書記載(2.4〜3.6%)よりも高いこと、男性のみ服用で不妊が起こることについて記載がないが、起こりうる。これらの重要な情報を、患者に提供する必要がある。


LEAVE A REPLY