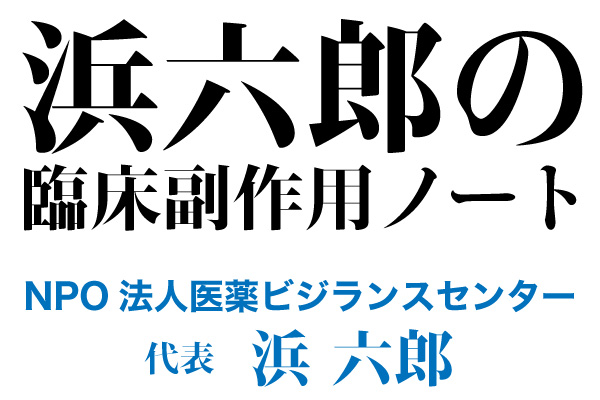
日本神経学会の2002年のパーキンソン病診療ガイドライン(02ガイドライン)では、早期のパーキンソン病は「日常生活に支障がなければ、そのまま観察してよい」としていた。ところが、18年ガイドラインは「不利益に関するエビデンスがないため」「診断後できるだけ早期に治療」を推奨している。その根拠を精査したところ、早期治療開始は、認知症の早期発症を誘発する危険性が高いことが判明した。薬のチェック921)号で詳細に検討した結果の概要を紹介する。
パーキンソン病の治療の基本はドパミン補充
今ではほとんど用いられなくなった抗コリン剤を除くと、抗パーキンソン剤(抗パ剤)のほぼすべてはドパミン系である。1) L-ドパ製剤:レボドパ+カルビドパなど、2)ドパミン作動剤:ブロモクリプチンなど、3)ドパミン部分作動剤:プラミペキソールなど、4)MAO-B阻害剤):セレギリン、ラサギリン、5)COMT阻害剤:エンタカポン、6)ドパミン遊離促進剤:アマンタジン、ゾニサミドなどである。
平均余命に差はないが認知症合併率が増加傾向
日本におけるパーキンソン病患者の平均発症年齢は約67歳で、発症後15年まで余命は一般人口と変わらない。一方、パーキンソン病には基本的に認知障害はない、と当初は報告されたものの、認知障害を起こすことがその後報告されてきた。抗コリン剤時代(1962)、ニュージーランドのウェリントン市の全パーキンソン病患者(83人)に対する調査では、平均8年経過時点で7人(8.4%)に認知障害があった。
抗コリン剤系抗パ剤を10年間使用すると認知症が約2倍に増加するとの報告がある(本稿第110回)。
次世代の抗パ剤ブロモクリプチンとL-ドパを比較したランダム化比較試験(RCT)対象者を20年間追跡した調査では、認知機能低下が5年後に15%、10年後には45%と、抗コリン剤より増加が著しかった。
さらに、新しい抗パ剤MAO-B阻害剤の使用を診断後すぐ開始した群(早期開始群)と、6か月遅れで開始した群(遅延開始群)で、72週間後(約1.4年後)のパーキンソン症状を比較したADAGIO試験をその後も追跡し、合計約4年後の認知障害合併率を比較した報告がある。1.4年後とその後に分割して報告されていた合併率を合計すると、遅延開始群でも約3.5年で43%、早期開始群では4年で53%と高頻度に認知障害を合併していた。なお、早期開始群と遅延開始群に運動機能の差はなく、ADAGIO試験対象者の平均年齢は、以前の調査とも差はない。
抗パ剤は興奮毒性を増強しうる
パーキンソン病は、興奮物質ドパミンによる興奮毒性で、脳の黒質の神経細胞が脱落・炎症を起こすため発症すると考えられている。したがって、早期の特に強力な薬物治療はドパミン過剰で神経細胞の脱落・炎症を増強させ、逆にパーキンソン病の悪化や認知機能の低下を招きうると考えられる。
実地臨床では
「診断後できるだけ早期に治療」との画一的な方針は不適切であり、日常生活に支障がなければ経過観察とした02ガイドラインが適切である。個々の患者の日常生活などQOL(生の質)2)と症状の進行具合とのバランスを考慮しながら、治療開始時期は個別に決定することを推奨する。過剰な治療は逆に悪化を招くので不適切である。


LEAVE A REPLY