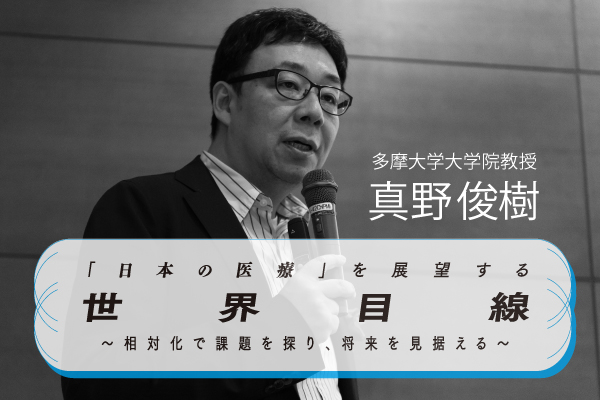
前稿では、アジア諸国を中心に医療ツーリズムの受け入れ実績や制度的背景について見てきた。続く今回は、自由競争原理の下で独自の医療展開を見せる米国の現状を取り上げる。
米国の状況
アメリカの制度・政策:米国は基本的に自由競争と市場原理に任せた形で医療を展開している。したがって、政府による組織的な誘致策はないが、メイヨー・クリニック、MDアンダーソンがんセンター、ジョンズ・ホプキンズ病院、クリーブランド・クリニックなどの著名な病院は、それぞれ国際患者部門(International Patient Services)を設置し、外国人患者の受け入れをビジネスとして確立している。もっとも、これについては多民族共生の米国では、国内にも様々な人種が住んでいるので、その対応ともいえよう。
富裕層外国人は通常の観光ビザで入国し、全額自費もしくは母国政府・保険からの支払いで高額医療を受ける。中東の王族や新興国の富豪などが最新の手術を求めて渡米するケースが典型例である。一方で、米国民の海外治療渡航(アウトバウンド)も増えており、近年いくつかの米保険会社や企業が従業員の医療目的渡航費を補助する試みも始まっている(例:ウォルマート社が従業員の心臓手術をタイで受けさせるプログラムなど)。法制度面においては、米国には医療目的に特化したビザ制度は設けられていないが、観光ビザの申請に際して治療計画書や資金証明等の必要書類を提出することで、比較的長期の滞在を伴う医療サービスを受けることも実質的に可能となっている。
また、国際的な医療機関評価の枠組みとして、1990年代に米国で創設されたJoint Commission International(JCI)は特筆に値する。JCIは本来、医療ツーリズムを前提とした認証制度ではないものの、医療の質と安全性に関する厳格な基準を有しており、当該認証の取得が、保険者や患者による国際的な医療機関選定の1つの指標となっている。
総じて米国は、「外国人患者の受け入れ(インバウンド)によって収益を得る一方で、自国民の国外渡航(アウトバウンド)も顕著である」という、国際医療上の特異なポジションを占めている。制度的な枠組みや政策的誘導よりも、市場原理とニーズの動向が国際医療の展開を主導している点が、他国と一線を画している。中国においても、今後は同様に「受け入れ」と「送り出し」の双方が本格化し、2方向の医療交流が進展すると筆者は予測している。

医療ツーリズムの経済的・社会的インパクト
医療ツーリズムは、特にアジア新興国のような受け入れ国にとって経済的メリットが大きく、波及効果が報告されている。例えばタイの医療ツーリズム市場は2019年時点で約90億ドルに達し(世界全体シェアの2〜7%)、インドも同年に約70万人の外国人患者を迎え入れ、約60億ドル相当の市場を形成したとされている。マレーシアも19年に130万人弱の医療旅行者を受け入れ、約17億リンギ(約500億円)の収入を上げた(マレーシア保健省報告)。
アメリカの場合、外国人患者を受け入れる40の医療機関の調査で、年間総計29億3000万ドル(約3200億円)の売り上げを計上したとのデータがある。日本でも潜在市場規模は大きく、10年に発表された政策投資銀行の試算によれば、20年までに約5500億円の市場規模、約2800億円の経済波及効果が見込まれるとされていた。中国に至っては、中国人患者が海外で支出する医療旅行費用が年間2〜3兆円規模に達しているとも推計され、これは言い換えれば中国国内で取りこぼしている経済機会であるといえる。日本でも統計には出ていないが、再生医療・人間ドックなどの現場で、中国人やベトナ人などの富裕層が訪れ高額な治療費を支払っているようだ。
経済効果の内訳を見ると、医療費に加え宿泊・観光・交通・通訳などの付帯消費が大きな割合を占める。医療ツーリストは一般観光客より滞在期間が長く、術前検査から術後の経過観察・療養まで含めると長期滞在による出費が地域経済を潤す。外科手術目的の患者は平均数週間滞在し、その間のホテル代や付き添い家族の観光支出などが地元にも利益をもたらす。
このため、タイやシンガポールでは高級ホテルと病院を直結させたサービスが展開され、地域の雇用創出にも寄与している。さらに、医療ツーリズムは民間医療機関の新たな収益源となり、最新設備導入や専門医の招聘のような利益の再投資を促す。外国からの治療費収入はサービス輸出として貴重な外貨獲得源となり、経常収支の改善や医療・観光産業の国際競争力向上につながる。
一方、社会的インパクトとしては医療サービスの国際化による技術・人材交流の活性化が挙げられる。海外患者の受け入れを通じて異文化対応力や英語コミュニケーション能力を備えた人材が育ち、国内医療従事者のスキル向上につながるとの指摘がある。また外国人患者のニーズに応える中で、院内表示の多言語化や患者支援ボランティアの組織化など医療環境のバリアフリー化が進み、結果的に日本人にとっても利用しやすい病院づくりに寄与する面もあろう。
しかし、経済効果の裏返しとして、受け入れ側の社会的コストやリスクも考慮が必要になる。例えば、「外国人富裕層の受け入れに病院が注力しすぎると、自国民の診療が後回しになるのではないか」という懸念がしばしば提起される。
特に日本では、国民皆保険制度の下で公平な医療提供が大前提のため、収益性の高い自由診療に人員を割きすぎて日本人患者の診療に支障をきたさないよう注意が求められる。タイでも公立病院の医師が高給な民間病院へ流出し、地方の医療人材不足が悪化する懸念が指摘された。このように医療ツーリズムには、「医療資源の国内偏在や流出」を招く可能性もあり、経済効果とのバランスを取った政策運営が求められる。
国際保健の観点から見ると、医療資源の活用において「国益」と「国際益」のバランスをいかに取るかは、きわめて繊細な課題である。日本政府は近年、「医療ツーリズム」から「医療インバウンド」へと呼称を改めている 。これは、医療の観光化や営利化に対する批判を回避しつつ、外国人患者の受け入れを経済戦略として推進するための措置と考えられるが、医療インバウンドの振興は、結果として国内の医療資源の商業的利用を拡大させるものであり、2010年前後にも強く指摘されたように、公平な医療アクセスの確保や国民皆保険制度への影響といった副作用をもたらす懸念は依然として払拭されていない。
医療インバウンドについては、すでに他国が一歩以上先を行っており、「追いつく」だけでは存在感は示せない。一方、医療を外交資産とするには、単なるプロモーションや制度批判ではなく、継続的な制度設計力と、医療現場を巻き込んだガバナンスが不可欠である。また、グローバルヘルス分野でのリーダーシップを本気で担う覚悟が求められるだろう。
医療ツーリズムの先行きについては、次回以降に述べていきたい。
参考資料
mediphone「医療ツーリズムの現状|世界・日本の状況や問題点を解説」2024年11月他 https://mediphone.jp/articles/medical-tourism
フロンティア・マネジメント「コロナ禍を経た『メディカルツーリズム』の行方」2022年9月他 https://frontier-eyes.online/medical-tourism/
日本政策投資銀行レポート 植村佳代「進む医療の国際化〜医療ツーリズムの動向〜」『総合健診医学』39巻6号, 2012
U.S. International Trade Commission, Medical Tourism 2015
Patients Beyond Borders Fourth Edition: Everybody's Guide to Affordable, World-Class Medical Travel Paperback – January 20, 2020 by Josef Woodman
How to evaluate surgical tourism service organizations in China: indicators system development and a pilot application 2022


LEAVE A REPLY