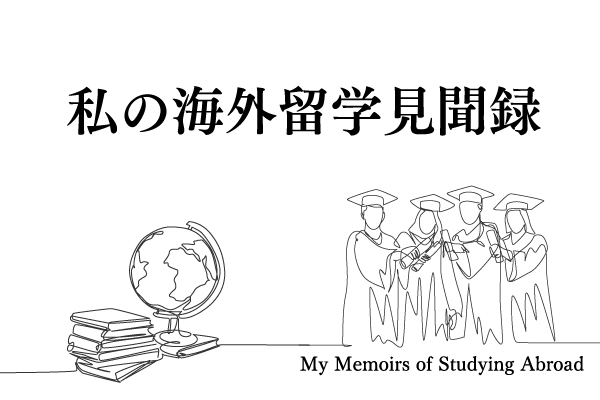
坂本 渉 (さかもと・わたる)
福島県立医科大学会津医療センター消化器外科学講座 主任 教授
留学先: National Institutes of Digestive and Diabetes and Kidney disease(NIDDK) , National Institutes of Health(NIH)(2011年10月〜14年3月)
留学まで——人生何が幸いするかわからない
「この中にお医者さまはいらっしゃいますか?」と言われた時に前に出られる医師になりたい。何よりも「取ったどー!」とガッツポーズができる医師になりたかった私は、2002年母校の福島県立医科大学で、当時の竹之下教授(現福島医大理事長)が「これからはがんと遺伝子の時代だ」と自らPRしていた第2外科に入局。丁寧かつ無駄のないご指導のおかげで08年には学位を取得させていただきました。竹之下教授は常々若手に留学を勧めていました。「医者じゃない、言葉も通じない、そういった状況に置かれたことのある人間だけに見えてくる世界がある」という言葉に強く興味を惹かれたものの、既に結婚し一児をもうけ、妻も反対。自分には縁がなかったと一度は諦めました。
大学院卒後3年の11年3月11日、郡山市の病院で、研修医に腹腔穿刺の指導中に、東日本大震災が発生しました。家には4歳・2歳・0歳の3人の子供がいましたが、幸い家具が壊れたり停電・断水になったりした程度で済みました。しかし、翌日の福島第一原発の水素爆発で、どこまで拡大するかわからない放射線被害への不安が募り、13日は朝から福島空港に並び、臨時便のチケットを手に入れて、妻と子供たちを北海道に移住していた両親のところに避難させました。
「留学、行きたいんでしょ? 行くなら今なんじゃない?」避難中の妻から電話がありました。そんな都合よく行くはずはないと思いましたが、たまたま手術指導に来院していた竹之下教授にダメ元で思いをぶつけたところ、「ちょうどNIH(米国国立衛生研究所)の日本人研究者の団体が、被災した研究者を受け入れると言っているんだ」とおっしゃいました。そして、NIHから帰国したばかりの先輩の齋藤元伸先生(現福島医大がんゲノム診療部教授)が現地の日本人研究者と交渉して下さって、無給のSpecial Volunteerでよければ、と声をあげて下さったのが、受け入れ先となったNIDDK(国立糖尿病・消化器・腎疾病研究所)のJürgen Wess博士でした。後で理由を聞いたところ、博士の奥様が日本人で、被災科学者の受け入れに積極的であったこと、「日本人の外科医ならとてもよく働くはずだ」と思っていたこと、また息子さんが我が家の長男と同い年で、日本人の友達が欲しいと思っていたからとのことでした。つまり「震災」と「長男の存在」が私の留学を決定づけたわけで、人生何がきっかけで好転するかわからないものです。
とmy-bossのDr.-Jürgen-Wess(右)-強化-SR.jpg)
異例のスピードで留学が決まり、10月には渡米しました。NIHはワシントンD.C.に接したメリーランド州ベセスダにあります。3人の子供を抱えた13時間のフライトでしたが、NCI(米国国立がん研究所)に先に留学していた医局の2人の後輩(岡山洋和先生・早瀬傑先生)が出迎えてくれ、apartmentも「あとはサインをするだけ」の状態にしておいてくれたので、渡米当日に入居することができました。さらに、その日のうちにCarMax(中古車屋)で車を手に入れて、その車で家財を購入し、持ち帰るという荒技も実現しました。昨今何かと敬遠されがちな「医局」ですが、留学先を決めてくれた齋藤先生といい、私の留学は医局の強力なサポートがあってこそでした。
コミュニケーションのターニングポイント
それでも最初は試練の連続でした。電気・ガス・インターネットの契約、子供のelementary school、nursery school入学、driver’s licenseの取得などなど、英語が流暢ではない自分にとっては困難の連続で、スムーズにはいきません。典型的日本人マインドであった自分は、うまくコミュニケーションが取れないことがある度に、「ああ、自分の英語がダメだからだ……情けない」と落ち込み、さらに自信をなくして喋れなくなる、という負のループに陥っていました。しかし、ひょんなことから転機が訪れます。何かの手続きで、窓口担当に、うまく喋れない私を明らかにバカにした態度を取られた時、ドラゴン○ールの悟○のように、私の中で何かが弾けたのです。「確かに俺は英語は下手くそだけど、日本語は流暢だし、学はある。バカにされるような覚えはない!」「Second languageで生活しているんだ、すごくないか?」。そうしたら急に目の前が明るくなり、コミュニケーションが取れるようになったのです。「Second languageだもん、いいじゃない!」。これは英語で苦労しているすべての日本人に伝えたいことです。いつまで経っても間違いだらけの英文で喋っているという副作用は出ましたが、英語でのコミュニケーションに対する恐怖は払拭されました。
ラボでは
「不純な気持ち」、かつ急に決めた留学のため、研究テーマは私にとって全く新しい分野となりました。研究自体は好きであり、テーマが自分の専門分野と異なること自体は苦にならなかったのですが、Special Volunteerで給料はなく、「聞き取れない」「喋れない」「研究内容わからない」の三重苦でしばらく途方に暮れていました。しかし、「日本人であること」「外科医であること」が道を切り開いてくれました。
まず日本人というだけで、明らかに信頼されました。そして外科医のため手先が明らかにラボメイトよりも器用でした。マウスに麻酔をして、総胆管や門脈をクランプしてコラゲナーゼやウイルスを注入するという実験もあったので、非常に重宝されました。しかも、与えられたマウスモデルで大きなフェノタイプが出るという幸運も重なり、日本学術振興会(JSPS)の海外特別研究員に採択され、渡航から1年3カ月で、ようやく収入を得ることができるようになりました。
家族との貴重な経験
JSPSを得てからは、圧倒的に生活が楽になり、家族がいても人並みの生活を送れるようになりました。毎週末は家族と過ごし、Niagara Falls、New York CityやOuter Banksなど、どこにでもロングドライブしました。飛行機での国内旅行にも挑戦し、フロリダのディズニーワールドへの7泊8日の旅では、最終日にディズニーマラソンにも参加しました。中でも最高だったのは、なんといってもキャンピングカーを借りて7泊8日でグランドサークルへ旅したことでした。どこまでも続く荒野を、とんでもないサイズのキャンピングカー(クイーンサイズベッド入り!)で、子供と語りながらドライブする……今思い出しても代え難い思い出です。自身のライフワーク的趣味であるトライアスロンやマラソンの大会にも多数参加することができました。
しかし、自身のプロジェクトは時間切れで、在米中に結果を出すことは叶いませんでした。無念でしたが、ラボメイトの実験のうちの動物実験をほとんど手掛けたことで、多くのbig paperで共著として名を連ねることができました。私の留学は無計画であったため、キャリアアップには直接はつながりませんでしたが、一度きりの人生に燦然と輝く、私と家族にとってpricelessな経験となりました。若い先生方にも、チャンスがあれば迷うことなくチャレンジしてほしい、できればお金がかかっても家族と行ってほしい、と心の底から思います。



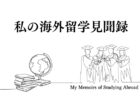
LEAVE A REPLY