
福水 道郎 (ふくみず・みちお)
東京家政大学子ども支援学部子ども支援学科 教授・狭山保健室長・
かせい森のクリニック 医師
留学先: Department of Psychology, University of Maine, USA(2003年4月〜05年12月)
2003年4月から05年12月までの2年9カ月、Maine州立大学心理学科のVisiting Scholar(後にResearch Associate)として留学しました。留学当時在籍していた国立精神・神経センター(NCNP)武蔵病院小児神経科では若手?の医師はある程度の期間研鑽した後、順次留学しており、私にも順番が回ってきた感じです。
その前に在籍していた東京医科歯科大学小児科医局神経グループでは、瀬川昌也先生との関係もあり小児睡眠を中心に研究していました。興味が深くなっていたことから、NCNPの医局の先輩神山潤先生(現・東京ベイ浦安市川医療センター管理者)に相談して、乳幼児睡眠研究が行える場所をいくつか紹介していただきました。その中でメールの返事が一番親切で、家族が住むのに治安もよく、自分が日本で手掛けていた夜泣きのアンケート調査研究を一緒にまとめてくれそうな心理学科准教授(後に教授)のHayes Marie J先生に絞ることに。受け入れの許可に加え、現・関西電力病院の立花直子先生のご指導で海外派遣助成も得られ、準備が整いました。
研究留学生活
米国の医学部がない地方大学の心理学科に日本人として単身留学したため、通常の研究留学とは多少異なる経験になりました。生活基盤を整えるまで2週間を要しましたが、現地の方々の親切に支えられました。日本で進めていた臨床研究を、Hayes先生のお力添えで2本まとめ、うち1本はNCNPの加我牧子先生と神山先生のご助力もあり、米国小児科学会誌『Pediatrics』に掲載されたことが最大の成果です。
Maine州立大学を本拠としながら州東医療センターのAllied Scientistとして出入りを許され、医学・医療に関連する研究を進めました。教授の確固たるステータスを培うためには、米国立衛生研究所(NIH)などメジャーなグラント(研究助成金)を獲得することが必要で、所属した当時の心理学科は獲得実績が大学の過半数を占め、学内トップレベルと誇られていました。それで私もHayes先生と共に2年くらい試みましたが、うまくいきませんでした。
グラントが取れず細々とした研究に終始しましたが、大学や州東医療センターのIRB審査を受け、メイン州の小児の1次ケアを担う家庭医・小児科医を無作為に抽出し、アンケートや訪問調査を行いました。項目は行動睡眠学的問題や睡眠時呼吸障害を中心に、診療連携、養育者指導、医療システムの課題などです。また2次的睡眠医療機関の役割に関する調査も行い雑誌に投稿しましたが、地域性の問題やサンプル数が少ないと片付けられて玉砕となりました。その後、他の調査も行いましたが、様々な事情があり、学部生の卒業研究としてまとめていただいたのが精いっぱいで、他は研究室のお手伝いで論文共著が数本という結果でした。
ただ、留学終盤に研究室で事象関連電位の研究を行うことになり機器の選定で日本製を薦めたところ、コストパフォーマンスとアフターケアの良さで採用され、購入後も喜ばれたので自国を少し誇らしく思いました。Hayes先生とは帰国後も長く交流が続き、先生が引退されるまで客員として電子図書館を利用させていただき、現在もたまにメールを交わしています。
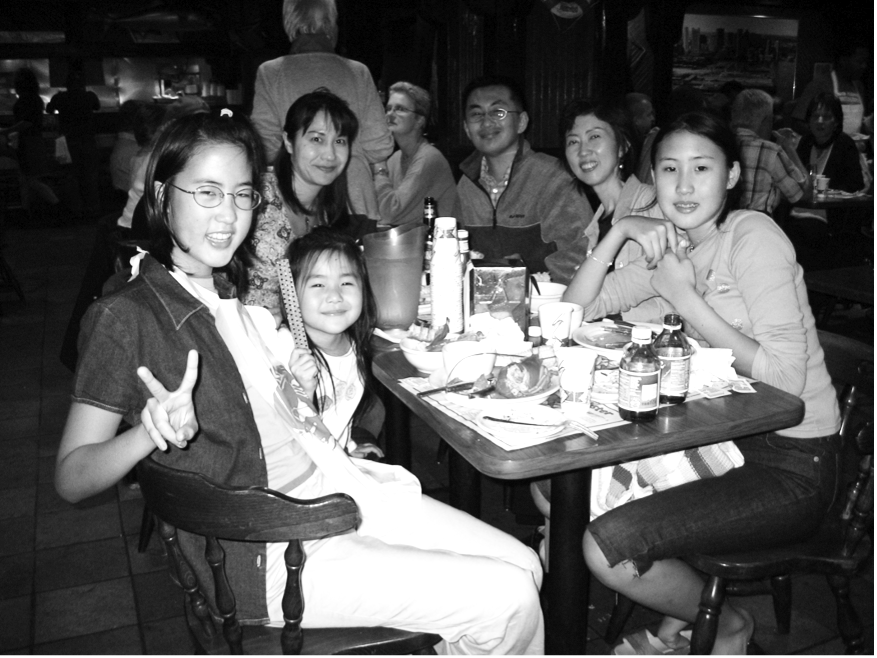
研究遊学生活
日本食のレストランで偶然 The Mount Desert Island Biological Laboratoryの日本人研究者と出会ったことがきっかけで、Maine州に設立されたヒトゲノム研究のグローバルリーダーでもあるThe Jackson Laboratoryの日本人研究者ともつながり、おそらく第1回となったMaine州の日本人研究者集合パーティーを開催することができました。Maine州立大学の他学部に留学した先生方とは帰国後も交流が続き、今も海洋科学部の先生と旧交を温めることができています。
元々訪問調査では州東地区の小児科や睡眠診療施設、重症心身障害児施設などの見学を予定していました。加えて、学内外で小児・神経科学関連講座を聴講しました。更に、New England地方で行われる医療従事者向けのトレーニングでは、小児睡眠障害について英語で講義を行うなど、貴重な体験が得られました。
米国の小児科クリニックでは、一般小児科医でもうつや神経発達症を診ており、複雑な症例は日本と同様に小児精神科医に紹介します。クリニックでは処方を行うのみで、輸液や処置が必要な患者は州東医療センターに送ります。診察では手品で子どもを和ませ、耳・目・側弯のチェックを丁寧に行っていました。独立した個室で待機する患者を医師が訪れる方式で、プライバシーは完全に保たれていました。電子カルテ導入直前の当時では、医師はカルテを持ち歩かず、後でカルテにメモを貼付していました。
重症心身障害児施設では、利用者の日常ケアのみが行われ、レスパイト利用(自宅で介護する家族が休息を取れるようにするための短期間利用)が多くを占めていました。また、当時の日本と違い移乗は全て電動介護リフトで行われ、輸液等が必要な場合は医療センターに搬送されていました。加えて、利用者は医療センターの総合診療医による回診も毎日受けていました。一方で、入所者は成人年齢までという制限があったため、成人に達しても行き場がなく入所を継続している人もいて、その親御さんに「日本では年齢制限がない」と話すと、本当にうらやましいと言われました。とはいえ、米国の小児科クリニックや障害児施設は当時の日本より進んでいる点が多く、様々な事柄を習得することができました。
留学中の「失敗体験>成功体験」が今に役立っている
米国滞在経験の中で私が最も重要視したのは日米の違いを肌で感じ取ることでした。同じ小児神経科医でシカゴ大学に留学していた加藤光広先生や、ハーバード大学McLean病院に留学していた友田明美先生との交流も良い思い出で、州によって医療文化が異なることも多少体感できました。
英語力の不足は悔いが残りますが、Research Associateの昇格面接では、話しきれなかった点をメールで補足し理解を得られました。意思疎通をさらに強めたいというこちらの思いが通じ、正式な研究員として州のグラントで雇用されましたが、その際Office of Equal Employment Opportunityという差別偏見を受けないよう雇用を調整する部署が関わり、公正な判断が行われたのには驚きました。このように当時の米国では、思いがあれば道が開けるということがわかったのが一番の収穫です。
留学末期に『Pediatrics』の論文をきっかけにカナダのMcGill大学のCote Aurore先生から声をかけられ、帰国直後に乳幼児突然死症候群(SIDS)の国際学会のシンポジウムで日本人の乳幼児の睡眠環境について発表できたのも留学の成果であり、貴重な経験でした。現在の東京家政大学での教員生活でも、留学中の「失敗>成功」体験が大いに役立っていることは紛れもない事実です。
海外留学は滞在費や治安、帰国後のポストなどの問題もあり、躊躇する方が多くいらっしゃると思います。それでも、機会をとらえ長期間滞在し、様々なことを肌で感じ体験することも1つの選択肢になりうることを、多くの方に知ってほしいと思います。




LEAVE A REPLY