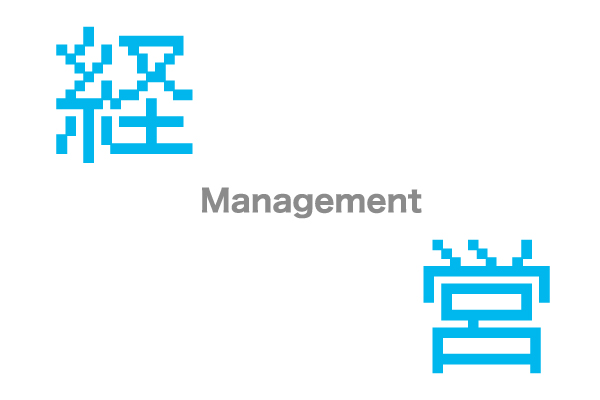
多角的に「死」を考えることでより良く生きる
世界に先駆けて超高齢多死社会を迎える日本。どのような社会を築いていけばいいのかを「死」をキーワードに考えようと、NPO法人健康医療開発機構が2018年10月、「超高齢多死社会を生きる〜“死を想う”ことから見えるもの〜」と題したセミナーを都内で開いた。 講師は、内科医として地域医療の充実を目指している占部まり氏。占部氏は世界的な経済学者であった故宇沢弘文・東京大学名誉教授の長女。
宇沢氏を2014年に自宅で看取った経験から、日本メメント・モリ協会を2017年に設立、代表理事を務めている。メメント・モリはラテン語で「死を想え」。同協会は、多角的に「死」を考えることでより良く生きることを考える場を提供している。
また、占部氏は宇沢国際学館の代表取締役として、宇沢氏が提唱した最も重要な概念である「社会的共通資本」など宇沢氏の理論思想の伝道師の役割も務めている。
宇沢氏は「日本で最もノーベル経済学賞に近い」と言われ、グローバリズムと新自由主義への警鐘を鳴らした。医療を社会的共通資本の大きな柱の一つ、制度資本として捉え、様々な提言を行った。日本病院会参与を務めたりもしていた。
終末期は何もしなければ楽に逝ける
占部氏が死に関して考えるようになったきっかけは、宇沢氏を自宅で看取ったこと。当時の占部氏は病院の臨床しか知らないこともあり、過剰な医療を行った。結局、宇沢氏は最期、苦しんだという。
そのことを終末期医療に関わる大井玄・東京大学名誉教授に話したところ、「何もしないであげたら、楽に見送れたのにね」と言われ、大往生という概念を知った。
その頃、勤めていた病院に、膵臓がん末期の90歳代の患者が入院してきた。食事を食べられないため点滴をしていたが、少しすると苦しむようになった。家族や医療スタッフと話し合って、点滴をしないという選択をした。すると、患者は「先生いつもありがとう」と言って、最期は眠るように亡くなった。それは恵みのような瞬間だった。
翻って、今の医療制度や医療状況を見ると、患者が亡くなる時はつらいことが多過ぎるのではないかと考えて、日本メメント・モリ協会を立ち上げた。患者や家族を含め、哲学者、宗教者、医療者などと死について多角的に話し合う中で、死を想うことで生を輝かせようという考え方に気付いた。
死をわざわざ取り上げることに疑問の声もある。これに対し、占部氏はバスケットボールに関する臨床実験の結果を示す。チームを二つに分けて試合をする。ハーフタイムにAチームには今までのゲームの反省点とこれからの抱負を書いてもらう。Bチームには死に関するリポートを書いてもらった。後半戦は、Bチームの方が得点率などが上がった。
占部氏は「人はリミットがあることを考えるだけでパフォーマンスが上がるらしい。そうならば、日常的に死を考えることは悪いことではないのでは」と話す。日本人は食事を食べる前に「いただきます」と言うが、これも「生命をいただく」というある意味、死を想いながら食事をしていると指摘する。
日本人の死因に関する統計も示した。以前は感染症など一つの原因が特定できる病気で亡くなっていたので、適切なタイミングで病院にかかれば助かる命も多かった。しかし現在は、悪性腫瘍や脳血管疾患など高齢化による複合的原因による死亡が大半を占め、同じ病名でも人によっては治療が効いたり効かなかったりする時代になった。
さらに、病院が多ければ、人々が健康になるわけではない。占部氏が示したデータでは、病床数と平均寿命には相関関係はなく、男性の平均寿命に至っては人口当たりの病床数が増えると短くなっているかのようにすら見える。一方、病床数と相関していたのは一人当たりの入院費だった。
また、今の社会福祉制度は高齢者が少なく、労働人口が多いバブル期にデザインされたものなので、少子高齢化の現在、制度を見直すべきと提案する。極端な話を言えば、高齢者の定義を85歳以上とすると、ほぼバブル期の労働人口と同じになるので、85歳まで働ける社会になれば、社会保障費の問題はなくなるのではないか、という。
実際、調査では79歳でも社会に繋がりを持ちたい、仕事をしたいという人は8割を超え、90歳以上でも男性の約1割は社会にコミットしたいという意思を持っている。
死は生老病死の最後にあるもの
健康には人間関係も重要だ。米国で急性心筋梗塞で入院した患者を調査したところ、1人も見舞いに来なかった患者の7割が死亡。1人見舞いに来た患者の死亡率は5割強に下がり、2人以上だと3割弱まで下がった。「これほどのインパクトを病院のシステムや治療法で起こすことは無理」と占部氏。
医療技術だけでは患者を救えない例として、同じく米国の研究を紹介した。猫の死骸などの不吉な物やきれいな風景などを取り混ぜた写真を二つのグループに見せた。科学技術の進歩で120歳まで生きると考えて見てもらったグループより、6カ月後に死ぬと考えて見てもらったグループの方がきれいな心地良い写真を心に留める傾向にあった。年齢別では、高齢になるほどその傾向があった。
占部氏は「私の高齢患者さんも些細なことにも喜びを感じ、周囲に感謝できるようになってきて、感情的な成熟がうかがえる。こういうことを考えると、死は敗北ではなく、生老病死を重ねた人生の最後にあるもの」と述べる。
安楽死の問題にも言及した。カナダでは2016年に医師の幇助による安楽死が合法化され、1年間で2000人近くが死去したが、そのことで医療費の節約金額が報じられたことに対し、「命とお金を天秤に掛けて政策とするのはどうなのか」と疑問を呈した。
認知症については「施設に入ると新たに記憶を積み上げていくことになるので、患者さんはつらい。一人暮らしの方が認知症周辺症状と言われる徘徊や暴言が少ないという印象を持つ医師も多い。二人暮らしは一番ストレスが多いので、たとえ一人でも日頃楽しく過ごしていれば、不整脈などで突然亡くなっても孤独死ではないだろう」と話す。
占部氏は今後の超高齢社会で重要になるのは事前看護指示書、かかりつけ医、医療後見人制度だという。ただ、指示書に本人が治療をしないと書いていても、緊急時に家族は納得できないと思われる。家族がいないような場合は指示書に記し、家族がいる場合はかかりつけ医が患者本人の希望を家族に伝え、この先の治療を勧めた方がいいと述べる。
占部氏は「命という言葉には物理的な命とは別に、物語れるものとしてのいのちがある。物語られるいのちは消えない。そうしたことが分かれば、家族は『何かあったら困る』ではなく、このタイミングで見送っていこうという気持ちになれるのではないか」と話した。


LEAVE A REPLY