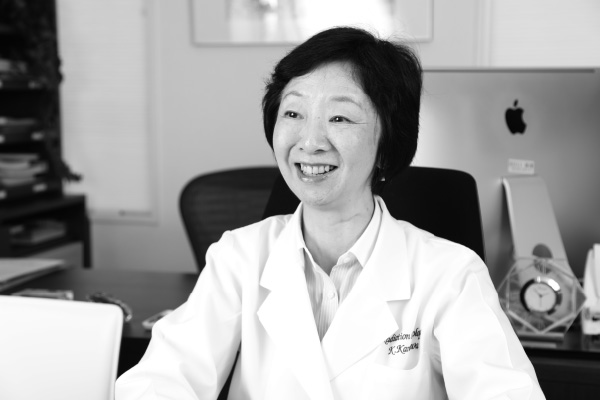

唐澤久美子(からさわ・くみこ)1959年横浜市生まれ。東京女子医科大学卒業。同大放射線医学講座講師、順天堂大学医学部放射線医学講座助教授、放射線医学総合研究所重粒子医科学センター病院治療課第三治療室長などを経て、2015年から東京女子医科大学教授・講座主任、2018年4月から医学部長。
東京女子医科大学 医学部長
放射線腫瘍学講座教授・講座主任
唐澤久美子/㊤
ある2月の日曜日、いつもよりくつろいで入浴中、乳房に触れた途端、尋常でない手触りを感じた。乳腺専門医である唐澤久美子には、それが何を意味するかはっきり分かった。落ち着いて確認すると、つい最近できたものではなく、2㎝以上はありそうだった。一瞬、衝撃を受けたが、恐怖を抱くことはなかった。「患者には、毎日の触診を勧めているのに、これはまずい」。先立ったのは、羞恥心だった。
半年前から、熱心に乳房に触っていれば、ささいな異常のうちに気付いたはずだし、自分なら3カ月前に確実に分かっただろう。しかし、この3カ月ほど、忙しさにかまけて触診を怠っていた。
風呂場を出ると、居間にいた夫に告げた。「私は、乳がんだと思うわ」。夫の克之は同じく放射線腫瘍医、一瞬驚いて顔を上げたが、平静を保っていた。
がん家系だが早期発見で対処
唐澤の身内には、がん罹患者が多い。母は乳がん、父は大腸がんで、乳がんは大おば、そして妹もかつて患っている。父方の祖母は子宮がんでおじは腎がん、母方の祖母は卵巣がん、いとこはリンパ腫や肉腫だった。
「家族内にがんが集積する、“がん家系”で、いずれ自分も100%がんに罹ると予想しており、50代までならなかったのは、むしろ不思議だった」
乳がんの場合、一つの遺伝子変異が親から子へと伝わって発症する遺伝性乳がんは全体の約10%。唐澤が遺伝子検査を受けても、主要な遺伝子変異は発見されなかった。それでも、発症に繋がる遺伝的素因を受け継いでいると考えられた。
2人の祖母やいとこはがんで亡くなったが、それ以外は早期発見で対処でき、80代の母親も健在だ。早期であれば生命予後への影響が低いことは、診療を通じても家族のこととしても実感できていた。
乳がんはいくつかサブタイプに分類され、治療法も異なる。全体の7割を占めるのがホルモン受容体陽性のルミナルAタイプで、増殖能力が低く、ホルモン療法が推奨されている。一方、同じくホルモン受容体陽性でもBタイプは、増殖能力が高いため、ホルモン療法に加えて化学療法も行うことが一般的だ。3カ月間の増殖スピードを考えると、ルミナルBである可能性も高そうだった。
造影剤をはじめとして、薬剤に対するアレルギーや過敏反応を持っているため、体への負担が多い抗がん剤治療は避けたいと思っていたが、それは難しいかもしれない。がん罹患に次いで二つ目のショックだった。
唐澤は、母方の実家がある横浜で生まれ、国家公務員だった父の転勤で長野や新潟を移り住んだ後、東京で育った。医師を目指したのは、母の影響が大きい。東京女子医大を卒業した母は愛校心が強く、娘も母校で学ばせて医師にしたいと考えていた。期待に応え、母の辿った道を追い掛けた。女子医大に入学した頃、母は開業して、小児科医としてアレルギーを専門にしていた。
日本のがん患者は増え続けていた。唐澤はがんを最も克服すべき病気と考え、がんを治す医師を志願。ただ、外科は性に合わないと感じていた。
大学時代に所属していたゴルフ部で、顧問を務めていた田崎瑛生は、放射線医学総合研究所から着任、放射線腫瘍学分野を牽引した。唐澤は、3年生の時、田崎の退任前の最終講義を聞き、放射線療法の前途に深い感銘を受けた。田崎は後に日本放射線腫瘍学会の初代会長となり、第1回学術大会は1989年に東京女子医大で開かれた。
日本は世界で唯一の被爆国のため、放射線に対する忌避感が強いが、欧米では放射線治療による根治術が行われており、唐澤はその可能性に目を見張った。後に夫となった克之は大学時代の美術サークルの仲間で2学年早く病院実習を始めており、放射線治療の面白さに目覚めていた。
唐澤が5年生になって臨床実習を始めると、血液内科では、抗がん剤を用いた化学療法が行われていた。しかし当時は、根治を目指せる薬がなく、毎日のように命を落とす患者に遭遇。血液内科医の仕事は厳しそうに思えた。一方、放射線腫瘍科では、がんが根治して退院していく患者に多く出会った。迷わず、放射線腫瘍医になることを決めた。
2人の子を育てながら専門を究め、母校で充実した日々を送っていたが、何度か病気に見舞われた。
まず、卒後5年で突発性難聴とめまいで入院。最初の外科手術はその3年後、良性腫瘍である神経鞘腫が頸部にできた時で、自分で触れてしこりを発見した。その後も2回手術を繰り返した末、反回神経麻痺から声帯麻痺が起こし、声帯にシリコンを注入。声は元通りにはならず、歌を歌うこともできなくなったが、仕事や生活はほぼ支障なく行えた。
その5年後には外来診察中に虫垂炎の激痛で血圧低下、外科に搬送されて緊急手術、助教授時代にも外来診察中に胆石で緊急入院し、腹腔鏡手術で胆嚢を摘出。教授就任後には虚血性腸炎になった。定期健康診断は受けており、こうした既往歴から2〜3年に1回CT検査も受けていた。
身辺整理の時間ある分「がんは良い病気」
さて日曜の晩に、乳がん、それも進行が速そうだと目星を付けたからには、一刻も早く確定診断をして、治療に繋げたかった。その日のうちに、同僚の乳腺科医師3人にメールを書いた。月曜に超音波検査、火曜にはMRI検査を受けた。いずれも、唐澤の診立てを裏付ける検査所見だった。水曜、外来を終えると、カンファレンスの始まるまでの10分間に、組織診(生検)を実施してもらった。
主観的にも客観的にも疑いようもない乳がんだったが、勤務先の病院で手術を受けることは立場上、人目もあることから、ためらわれた。そこで、日本乳癌学会の医師仲間の紹介で、自宅から最寄りの別の大学病院で治療を受けることを決めた。
確定診断はステージ2の乳がん。診断がついても、特に落ち込むことはなかった。
「人間は100%死ぬ。心筋梗塞や脳梗塞などで、急に仕事ができなくなるのに比べれば、もし予後が悪いタイプでも身辺を整理する時間がある。そういう意味では、がんは良い病気」。木曜に最寄りの大学病院を受診して翌週から外来化学療法を開始する予定を決めた。(敬称略)
【聞き手・構成/ジャーナリスト・塚崎朝子】




LEAVE A REPLY