
大企業の役員報酬・配当金プラスの一方、労働分配率は低下
「税金を下げた分で内部留保とは、なめちゃいかん」——。
麻生太郎・副総理兼財務相は2017年9月28日、都内の会合でこのように述べ、「法人税の減税後も賃上げや投資に慎重な企業経営者に怒りをぶちまけた」(時事通信10月6日の配信記事)という。
法人税減税の背景に企業献金の増加
正論を吐いたように感じなくもないが、いかがなものか。16年度決算で国の一般会計は前年度を8200億円も下回ったが、うち法人税は5000億円の税収減に見舞われており、下回った分の6割以上を占める。国の財政がここまで悪化の一途をたどりながら、「国際競争力」を理由に法人税減税を実施した妥当性が問われてもおかしくないが、この点について麻生は財務相としてどう考えているのだろう。
第2次安倍晋三内閣発足時の12年には、法人実効税率は37%だったが、16年度に29・97%にまで下げられ、さらに18年度には29・74%まで落ちる。無論、その背景には事あるごとに法人税減税を要求してきた自民党のスポンサーである財界の要求があり、同党に対する企業献金は同じく12年から16年の間に、1・63倍に膨れ上がった。
政治献金という名の“賄賂”を受け取り、それと引き替えにスポンサーの意向を受け入れた自民党の麻生が、今さら「なめちゃいかん」もあるまい。ただ、それでも麻生の言い分に一理あるように思えるのは、内部留保の問題があるからだ。
周知のように、17年9月1日に財務省が発表した16年度の法人企業統計によると、資本金10億円以上の企業の内部留保が、初めて400兆円を超えた。第2次安倍政権になって以降、約100兆円増えた換算になる。内部留保は、企業が将来のリスクに備えるために必要とされる面はあるものの、やはりその絶対額は、看過出来ない問題を提示しているように思える。
このため、「企業の儲け過ぎ」「従業員の給与に回せ」といった批判が生まれ、今回の総選挙前に結成されたばかりの希望の党も、「資本金1億円以上の企業の内部留保というものが300兆円ぐらいある。これに対して課税することで代わりの財源にしていく、こういったことも提案している」(当時の小池百合子代表)と述べ、公約として、「内部留保課税」を打ち出したのは記憶に新しい。
内部留保とは、税引き利益から税金を引いた後、配当を出して、その後に社内に残った利益を指す。ただ、必ずしも全て現金や有価証券ではなく、設備や土地、建物も含まれ、内部留保が膨らんでも、即、従業員給与のアップに転じることが出来るとは限らない。
それでも内部留保のうち、現預金だけでも16年度で約210兆円に達している。過去10年間で、75兆円もの増大だ。この点で、「企業の儲け過ぎ」批判は必ずしも的外れではない。『産経新聞』でさえ、「日本経済にとっても企業が持つ莫大な利益剰余金をどのように配分してもらうかは大きな課題だ。……特に賃上げに対しては産業界を挙げてもっと取り組むべきだ」(電子版11月12日付)と苦情を呈しているほど。
前出の麻生も、「(内部留保が)年々25兆円前後たまっているんだったら、その分は給与に回されたら」とも述べているが、これに対しては、「企業の活動に政府が口を挟むべきではない」といった、「自由主義経済」の立場からの反論が聞こえてくる。だが、明らかに見当外れだろう。
少しでも公共事業にありつこうと、財界やその中核企業が「真水」(GDPを直接増やす効果のある対策)がどうのこうのと予算編成期に口を挟むのは年中行事だ。
しかも、法人税減税実施のみならず、特定企業や業界のために一定の政策目的で税額控除や特別償却、所得控除を実施する租税特別措置の温存に象徴されているように、「企業活動」に「政府」が便宜を図るよう、「口を挟む」のを止めないのが彼らではないのか。
あのリーマンショック前、「アングロサクソン経営」や「自己責任」など「市場のことは市場に任せろ」といった類いの、ネオリベラリズムの言説が国内外で全盛を極めた。ところが、ウォールストリートに激震が走るやいなや、デトロイトを中心に各業界が真っ先に助けを乞うたのは、「アングロサクソン経営」では脇役であらねばならないはずだった政府だったのではなかったか。
これほど依存しておいて、今さら「口を挟むな」ではあるまいが、要は内部留保について論じられる以前に、リーマンショック後にようやく論議されるようになった「強欲資本主義」批判が、ここにきて跡形もないぐらいに薄らいでしまった現実にこそ、目が向けられねばならないのではないか。そして、その思いを強くするのは、労働分配率の低下に歯止めがかからない現状があるからだ。
労働分配率とは、企業の利益のうちの従業員の取り分だが、財務省の4〜6月の法人企業統計調査によれば、資本金10億円以上の大企業の分配率は43・5%で、実に約46年ぶりの低水準となった。12年と比較すると、12%ものマイナスとなっている。ちなみに、国民1人当たりの名目国内総生産(GDP)はマイナス20%である。
消費不況からの脱却は〝夢”か
一方で、同じ12年との比較では、大企業の役員報酬額が82%のプラスで、大企業の経営利益も63%のプラス。配当金も46%のプラスだ。大企業の内部留保はプラス20%を記録している。この明らかな非対称性こそ、話題に上る機会も失せるようになった「強欲資本主義」の姿そのものであるように思われるが、果たして日本経済にとって健全な現象なのか。
既に都市圏を中心に「人手不足」が深刻化し、17年度上期(4〜9月)決算では最高益を更新する企業が続出しながらも、給与の上昇率は微々たるものに留まっている。国税庁が発表した数字によれば、16年度における給与所得者の平均給与(年収)は約422万円だが、前年比ではわずか0・3%増に留まっている。これが15年度ではまだ1・3%であったのを考えれば、労働分配率が低下しないはずがない。
さすがに安倍内閣も事態の異常さを気にしてか、「18年度税制大綱で、賃上げ総額の一部を法人税額から差し引く『所得拡大促進税制』を拡充し、3%以上の賃上げをした企業には減税額を上乗せする方針』(『毎日新聞』電子版12月5日付)だという。だが、この程度の“エサ”を示したところで、今時の企業が17年春闘の賃上げ率1・98%をさらに上回る数字を実現するだろうか。
それでもここまで労働分配率が低いままなら、消費不況からの脱却など夢だ。リーマンショックから10年経つ18年は、「強欲資本主義」とは決して自ら姿勢を正すのを期待出来ない存在であるという事実を、改めて痛感する年になるのだろうか。(敬称略)


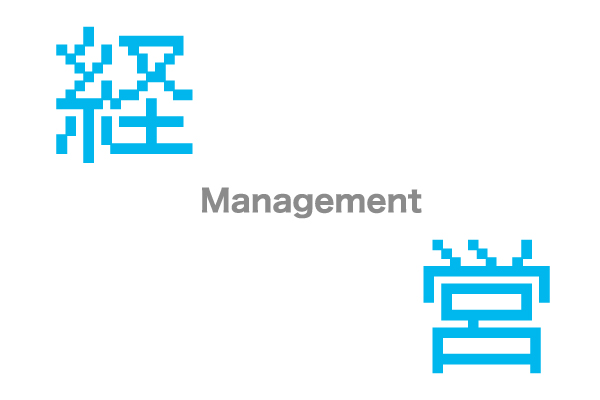

LEAVE A REPLY